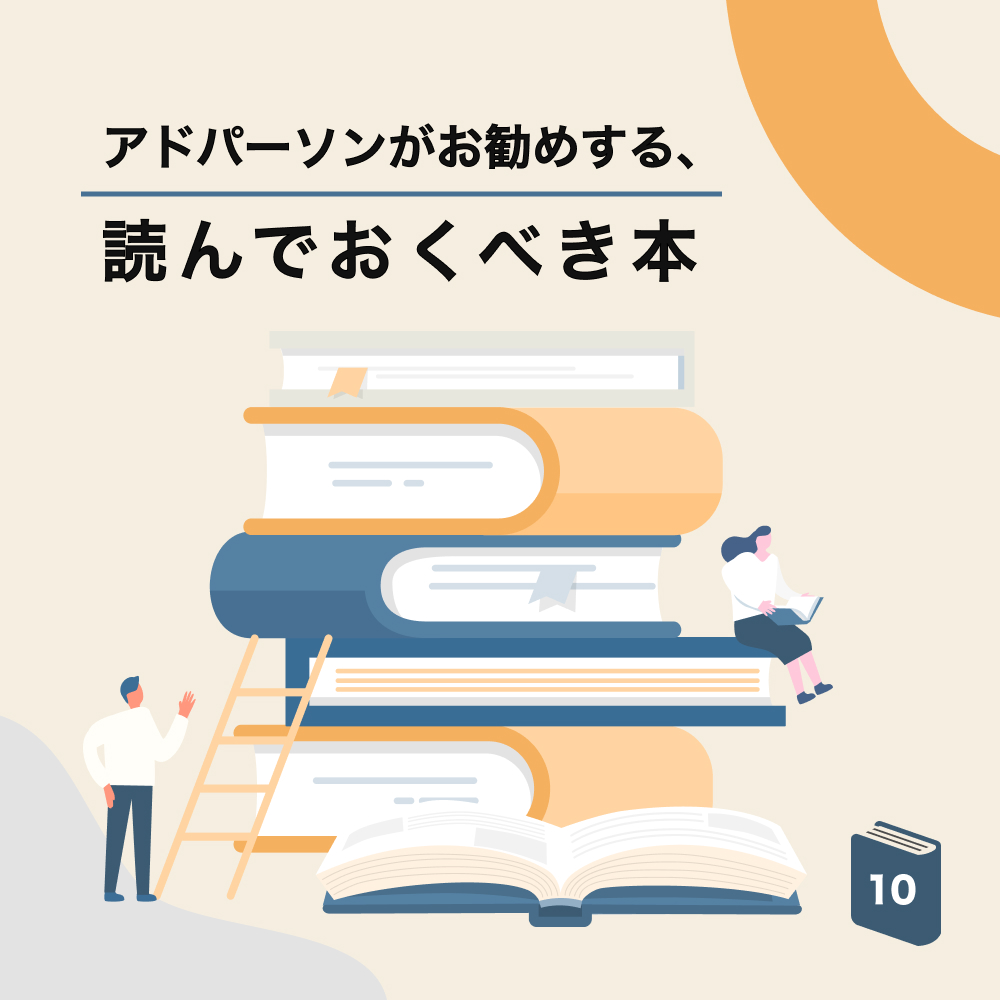令和シニア研究所 リーダー
10年以上にわたりデザイナー・ディレクターとして運用型広告に携わる。
現在は、テレビCMやWebCMなどの動画広告を中心に、クリエイティブディレクションに従事。確実に広告成果を上げる運用型テレビCMを得意とする。
2024年に「令和シニア研究所」を立ち上げ、シニア層のデジタルメディア活用やオンライン行動を分析。令和時代のシニアライフが活発で多様であることを明らかにし、シニア層向けのマーケティング活動を推進している。
前回は、70代までのスマートフォン保有率やインターネット利用時間の増加について紹介しましたが、背景には単なるテクノロジーの普及だけでなく、シニア層の“世代交代”があるのかもしれません。
第2回「シニアの『世代』が変化している?
〜かつて『新人類』と言われた令和のシニア」
前回は、70代までのスマートフォン保有率やインターネット利用時間の増加について紹介しましたが、背景には単なるテクノロジーの普及だけでなく、シニア層の“世代交代”があるのかもしれません。
1980年代に「新人類」と呼ばれた若者世代が60代に
アクティブシニアとしてイメージされやすいのは「団塊世代」ではないでしょうか。
1947〜1949年頃生まれのこの世代は、戦後復興と高度経済成長を背景に、終身雇用・年功序列のなかで「仕事に打ち込むこと」を美徳とし、家庭や職場での責任を重んじる傾向がありました。
一方、現在60代前半から半ばを迎えているのは、1980年代に「新人類」と呼ばれた世代です。親世代の価値観に反発し、個性や趣味を重視。バブル期に2、30代を迎えたこともあり、積極的に新しい文化を取り入れ、消費にも前向きでした。サブカルチャーの流行も相まって、“オタク第一世代”と呼ばれる世代でもあります。
さらにこの世代は、ゆとり世代からZ世代前半の子どもを持ち、「友達親子」と言われる対話的な関係性のなかで育児をしてきた背景もあります。こうした経験から、若年層に近い価値観やライフスタイルを自然と受け入れているのかもしれません。

世代的な価値観の違いが、消費行動にも影響
こうした価値観の違いは、消費行動にも表れています。
ロボット掃除機やスマートウォッチなど、QOLに関わる家電やデバイスの60代保有率が年々増加しているようです。
他方で、デジタル一眼レフなど、スマートフォンに代替されてしまいがちな商品の保有率は低下傾向を示しています。

また、前回も触れましたが、2024年のNTTドコモの調査(※1)では、シニア向けスマートフォン・ケータイの利用率が60代では13%にとどまり、大多数が一般的なAndroidスマートフォンやiPhoneを使用しているとされています。PGF生命の調査(※2)でも、60代の自覚年齢は実年齢より約10歳若いとされ、「まだシニアではない」という意識が、従来型の“高齢者向け”商品を避ける背景にあるのかもしれません。

まとめ
・ 1980年代に「新人類」と呼ばれた若者世代が60代に
・ 世代的な価値観の違いが、消費行動にも影響
こうした、世代間の価値観の違いをしっかりと捉えることが、これからのシニアマーケティングでは重要だと考えています。
次回は、世代交代しつつある令和のシニア世代が、ソーシャルメディアとどのように向き合っているかをお届け予定です。
※1 モバイル社会研究所(NTT)「2024年シニア調査」 https://www.moba-ken.jp/project/seniors/seniors20240624.html
※2 PGF生命「2020年の還暦人(かんれきびと)に関する調査」https://www.pgf-life.co.jp/company/research/2020/001.html