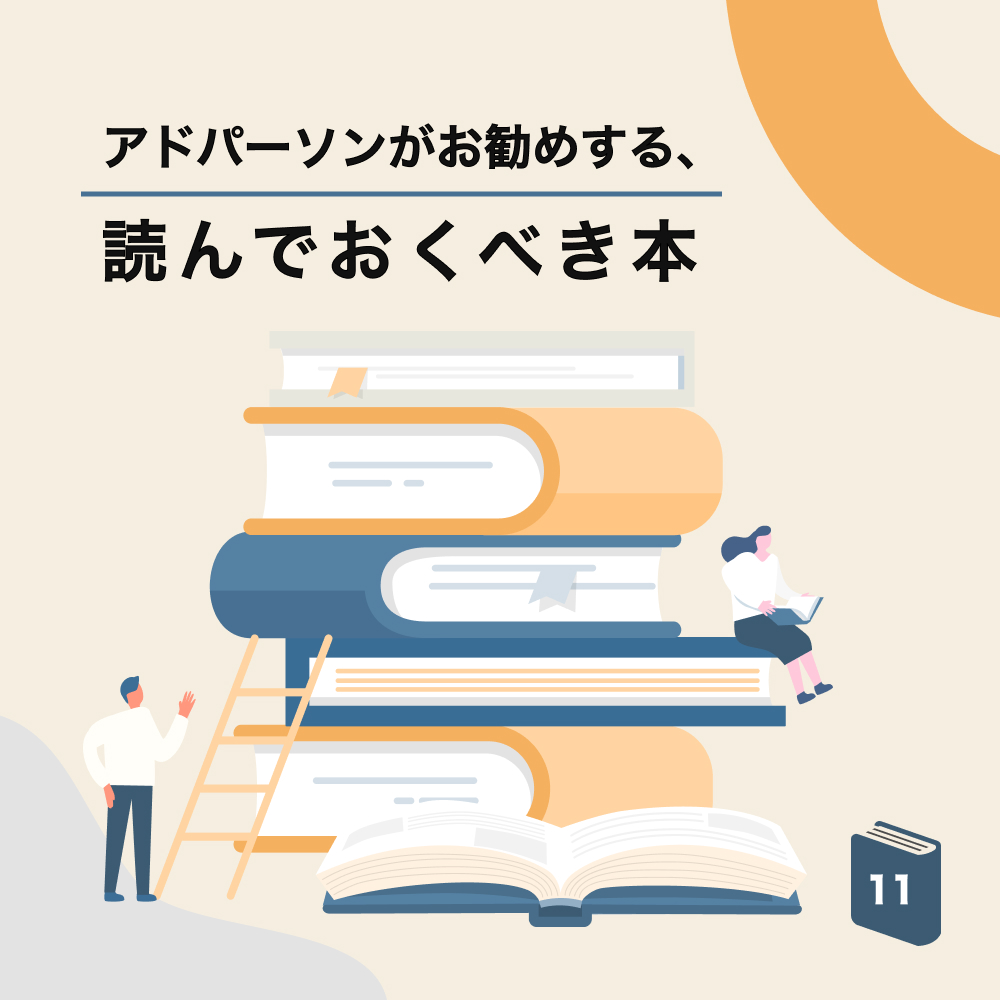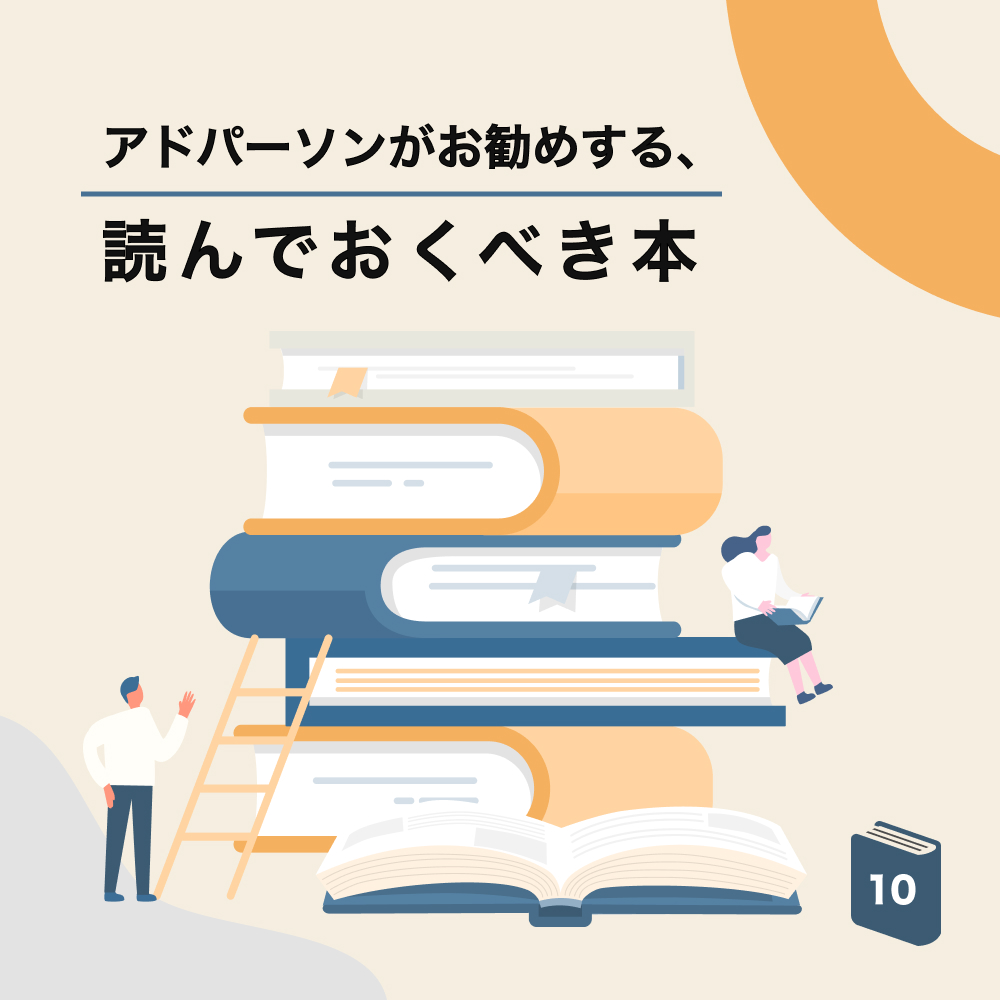令和シニア研究所 リーダー
10年以上にわたりデザイナー・ディレクターとして運用型広告に携わる。
現在は、テレビCMやWebCMなどの動画広告を中心に、クリエイティブディレクションに従事。確実に広告成果を上げる運用型テレビCMを得意とする。
2024年に「令和シニア研究所」を立ち上げ、シニア層のデジタルメディア活用やオンライン行動を分析。令和時代のシニアライフが活発で多様であることを明らかにし、シニア層向けのマーケティング活動を推進している。
近年、シニア層のデジタル化は急速に進んでいます。消費者庁の「令和5年版消費者白書」によれば、60代世帯のスマートフォン保有率は約9割に達し(※1)、7割弱がYouTubeを利用(※2)するなど、デジタル化はシニア層にも広がっています。
第1回「急伸長するシニアのデジ活」
近年、シニア層のデジタル化は急速に進んでいます。
消費者庁の「令和5年版消費者白書」によれば、60代世帯のスマートフォン保有率は約9割に達し(※1)、7割弱がYouTubeを利用(※2)するなど、デジタル化はシニア層にも広がっています。


こうしたデジタルリテラシーの高まりは、“グランフルエンサー”と呼ばれるシニア層のインフルエンサーの台頭だけでなく、多くの新しい取り組みやムーブメントを生み出し、新たな市場を形成しつつあります。
さらに、シニア層に広まりつつあるIT活用や、AIをはじめとした最新テクノロジーの進展は、地方創生や介護、医療といったシニア層の社会課題に対して、解決策や市場価値を生み出す原動力となっています。
本稿では、約一年にわたり、
シニア×デジタルの変化が市場にもたらすインパクトやビジネスチャンスを探っていきます。
急伸長するシニアのデジ活
デジタル機器の普及により、シニア層のデジタルメディアの利用時間も増加しています。
総務省の調査によると、60代のテレビ利用時間は前年比で減少し(-12.8分)、インターネット利用時間は増加(+10.5分)しています。
50代ではテレビとインターネットの利用時間が逆転し、60代以上でも同様の傾向が予測されています。YouTube利用率の増加もその一因です。

ただし、シニア層はエンタメよりも情報収集の目的でインターネットを活用する傾向が強く、特にYahoo!ニュースなどのニュースメディアや検索エンジンの利用が高いと考えられます。

一方で、スマートフォン利用においては、文字の小ささなどに不便さを感じ、指で拡大したり、メガネ・拡大鏡を使ったりする工夫が見られます。
令和シニア研究所の調査によると、85%のシニア層が使いづらさや見づらさを感じているとのことです。
一般的に45歳前後で老眼がはじまると言われていますが、シニア向けスマートフォンの利用率は低く、多くは一般的なAndroidスマートフォンやiPhoneを使用しています。
家族のサポートで利用をはじめるケースが多く、シニア向けスマートフォンの普及が進まない一因となっている可能性があります。
また、「シニア向け」商品に対して「自分はまだシニアではない」という意識が影響していることも考えられます。

まとめると、
・ 70代までのスマートフォン保有率が増加
・ インターネットの平均利用時間も伸長
・ YouTubeや検索エンジン、ニュースメディアの利用率が高い
・ 一方で、スマートフォンの文字の小ささなどの不便さを抱えている
ことがわかります。
シニア層へのデジタル技術の浸透とデジタルリテラシーの向上は、どのような市場を形成しているのか。
シニア×デジタルの変化が市場へ与える影響や新たなビジネスチャンスについて、次回以降の連載でさらに深く探っていきます。