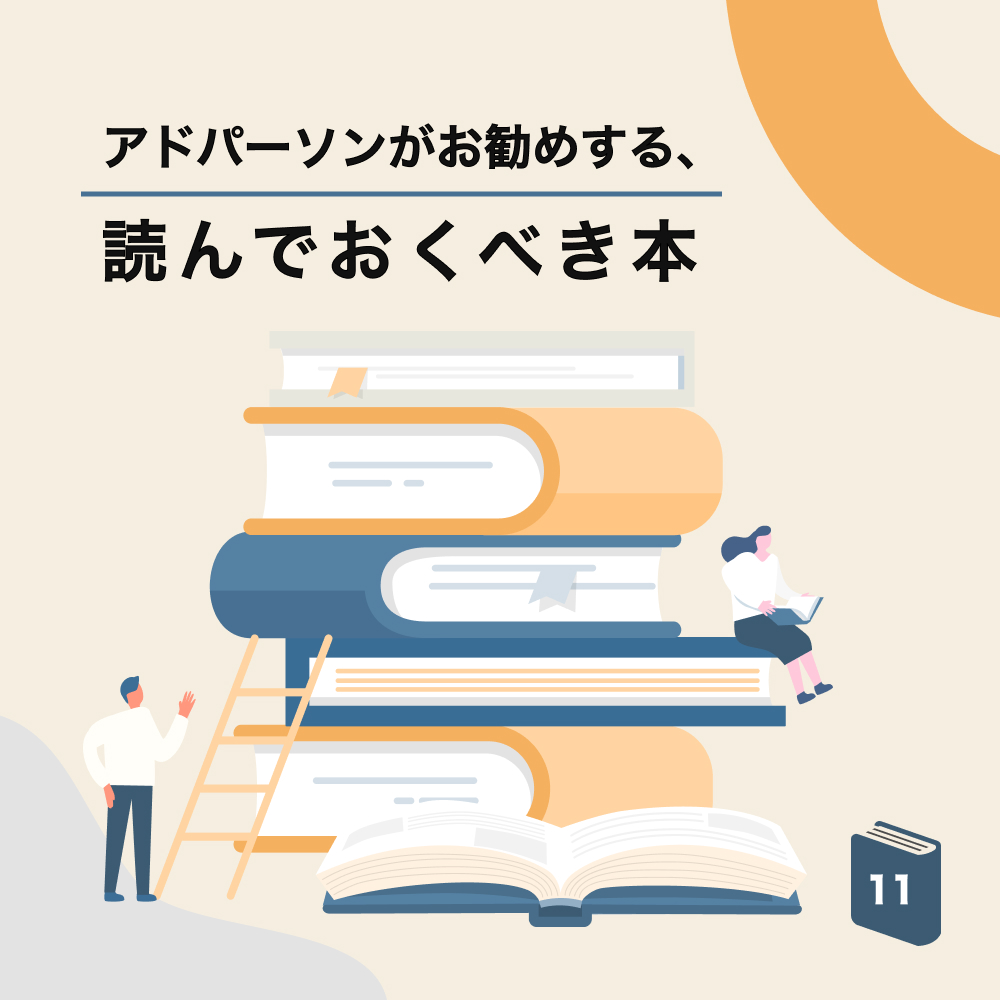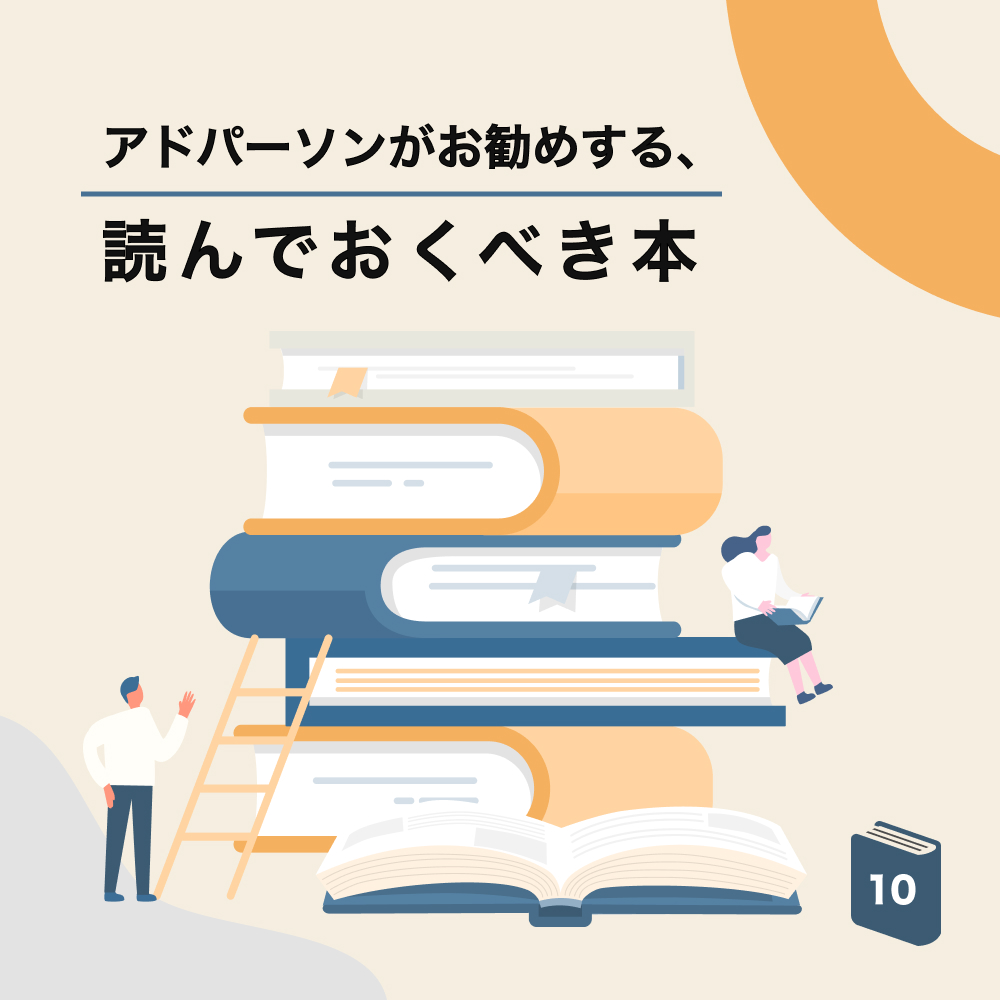1998年博報堂C&Dにコピーライターとして入社。
2002年に博報堂に転籍後はマーケティングプラナーとして自動車、嗜好品、飲料、化粧品等、幅広い業界のプラニングに携わる。2012年4月、博報堂生活綜研(上海)の設立とともに上海に駐在。2024年4月より、生活綜研(上海)董事長、博報堂(中国)首席代表を兼務。現在も各種研究、講演、ブランドコンサルティング業務などの領域で活動している。
近年の中国市場は、経済成長の鈍化や米中摩擦といった外的要因により、消費全体の回復が遅れています。政府の内需拡大策にもかかわらず、旅行や飲食など一部サービス分野を除き、生活者の購買意欲は依然として慎重な状況です。
中国消費の潮流:「機能」から「情緒価値」へ、マーケティングの「人感」視点への転換
近年の中国市場は、経済成長の鈍化や米中摩擦といった外的要因により、消費全体の回復が遅れています。政府の内需拡大策にもかかわらず、旅行や飲食など一部サービス分野を除き、生活者の購買意欲は依然として慎重な状況です。
そうした中で注目を集めているのが、IP(知的財産)やコンテンツを基盤とする中国発ブランドの台頭です。キャラクターグッズ「LABUBU」を展開するPOPMARTはその象徴であり、店舗では品薄が続いています。先日、アップルCEOのティム・クック氏が上海出張時に店舗を訪問したことも話題となりました。この熱狂は、中国生活者の消費心理が「機能価値」中心から「情緒価値」中心へと転換していることを象徴しています。
かつて中国の生活者にとって消費は、機能性やコストパフォーマンスの追求が主でした。しかし、経済的な成熟に伴い、その基準は「心の充足」へと移行しています。いま求められているのは、利便性や価格優位性ではなく、共感や誇り、安心、つながりといった感情的価値です。家族との絆や地域文化への誇り、ブランドとの共感的関係が、購買意思決定に強い影響を与えています。
特に若年層では、従来の「ステータス消費」から「自己表現型消費」への移行が顕著です。彼らは「私らしさ」を体現するブランドに惹かれ、短期的なトレンドよりも文化的背景や価値観の一貫性を重視します。
その特徴は以下の三点に整理できます。
- 「悦己(自己充足)」価値の追求: ブラインドボックスや新茶飲料の流行が示すように、消費自体が自己慰撫や愉しみのプロセスとなっています。
- 情緒価値と実用価値のバランス: 若者はコスト、品質、体験を理性的に比較し、納得感のある選択を志向します。
- 文化自信の高まり: 国貨(国内ブランド)は文化的アイデンティティの象徴として位置づけられ、特にコスメやファッション分野で外資系を凌駕する事例が増加しています。
こうした「情緒価値」志向の高まりの背景には、社会心理の変化があります。経済減速、雇用不安、不動産市場の停滞などから、若者を中心に将来への不安が拡大しています。また、競争や孤独感の増大が、心理的な安定や「癒し」を求める消費を後押ししています。
SNS上では“エモ消費”が急増し、小紅書(RED)や抖音(TikTok中国版)などでは、企業広告よりも共感性の高いレビューや体験談が、購買行動を左右する要因となっています。

このような市場変化に呼応し、企業のマーケティング活動にも明確な転換が見られます。そのキーワードは「人感(Human Touch)」です。抽象的なブランドスローガンから、リアルな生活者の感情や体験に寄り添うストーリーテリングへと移行。ブランドは単なる製品供給者ではなく、「温度」と「人格」をもった存在としてのあり方を模索しています。その方向性は次の三点に集約されます。
· 生活者を「ターゲット」ではなく「関係を築く相手」として理解する。
· 行動だけでなく、文化的・心理的背景までを読み解くインサイトの獲得。
· ブランドが「人」として語りかけ、共感を起点に関係性を構築する姿勢。
今後、AIやデータ技術の発展により、生活者理解の精度はさらに高まると見られます。感情分析やパーソナライズド体験の進化を通じて、ブランドと生活者の関係は単なる取引を超え、価値観の共鳴に基づく「共生関係」へと深化していくでしょう。
急速に変化する中国市場において、「人」に寄り添い、「情緒」を軸にしたブランド体験を設計できる企業こそが、次代に選ばれる存在となるはずです。