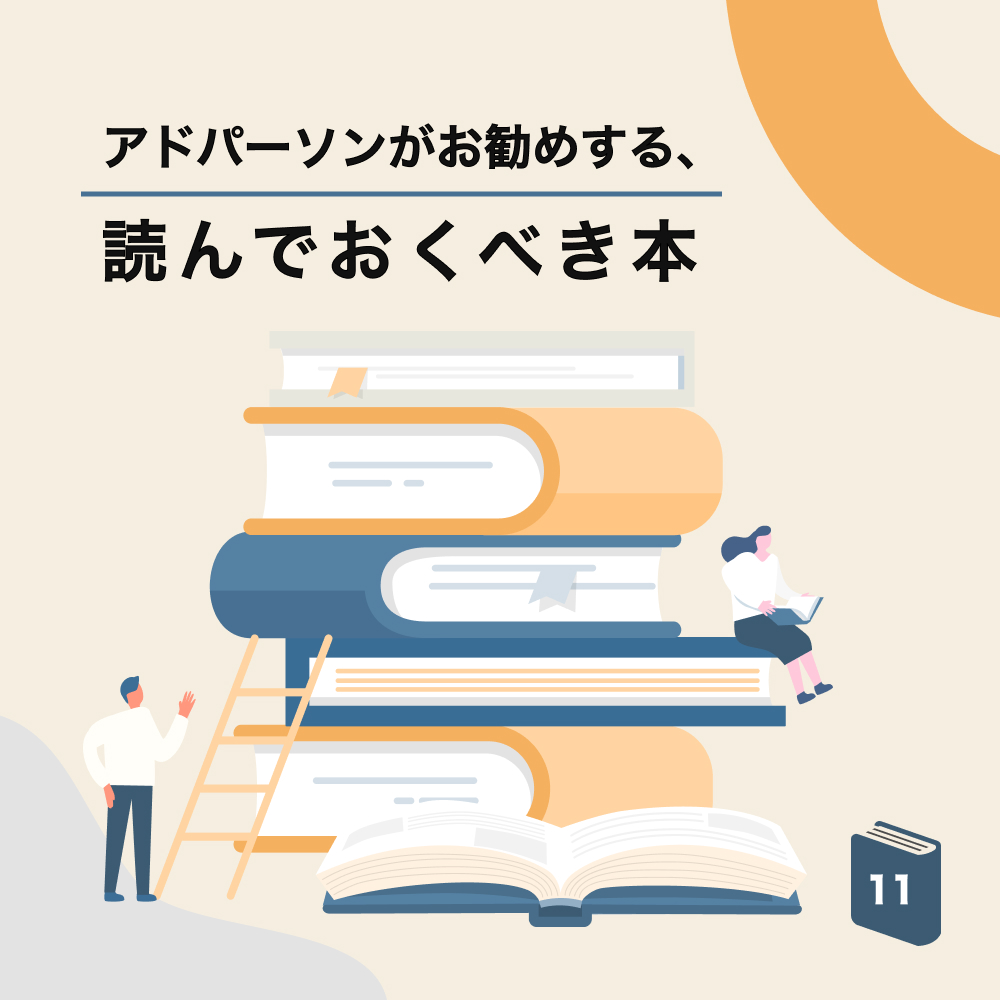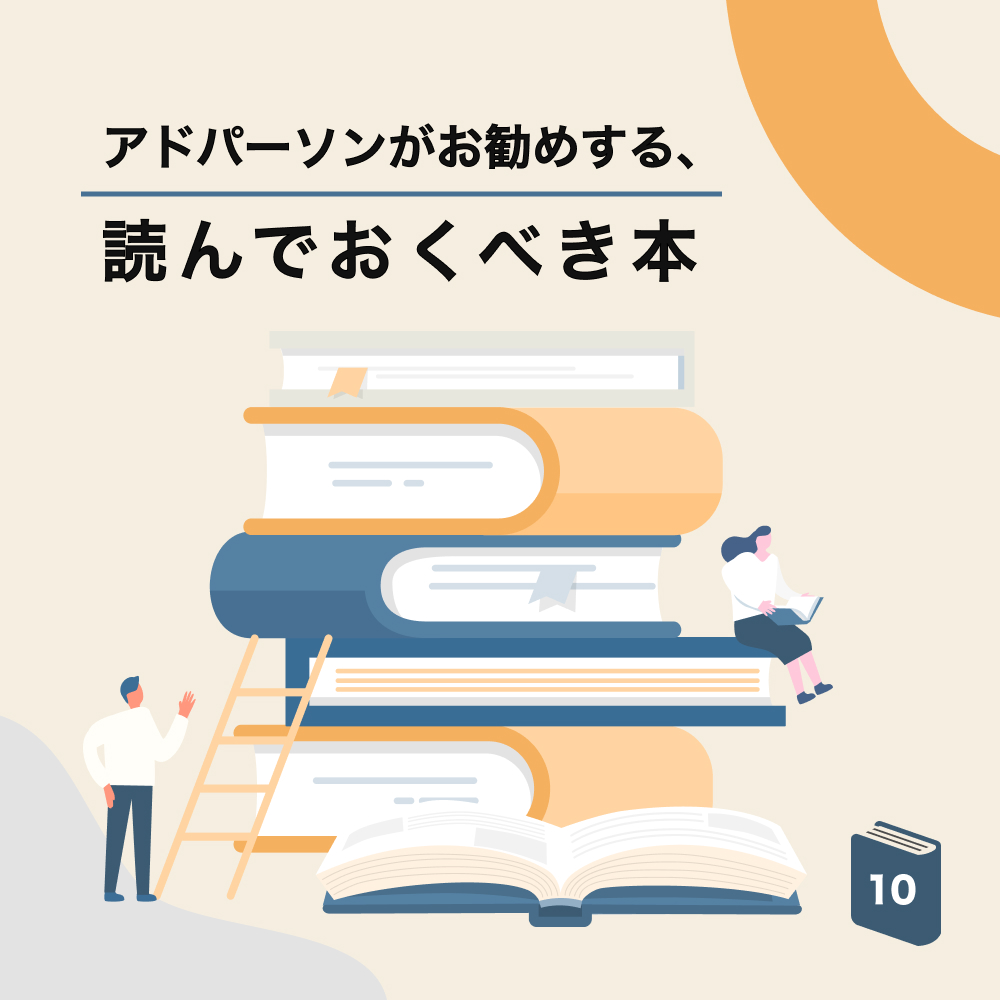上智大学理工学部物質生命理工学科卒業の後、新卒で(株)アイレップ(現 Hakuhodo DY ONE)に入社。
その後(株)デジタルガレージにてタイに駐在し、化粧品輸入販売事業に従事した後、2020年(株)大広に入社。
グローバルビジネス本部にて日系企業の海外進出支援・海外ECデジタルマーケティング支援業務を担当。
2022年より駐在員として台湾に赴任し、メディア、デジタル、SNS、イベントなど事業会社の広告戦略、商品戦略立案を支援。
2024年6月に日本へ帰任し、引き続き同業務を継続中。
昨今、東南アジアでマーケティングを行うにあたり意識すべきターゲットは、消費の牽引役となりつつある「新興富裕層」と定義される人達だ。
今アジアでのマーケティングにあたり重要なこと
〇「新興富裕層」へのアプローチ
昨今、東南アジアでマーケティングを行うにあたり意識すべきターゲットは、消費の牽引役となりつつある「新興富裕層」と定義される人達だ。中間層から一歩踏み出し、より豊かな生活を目指して努力を続ける人々のことを指し、博報堂生活総合研究所アセアンの調査では、新興富裕層の月収をタイであれば日本円で約27万~62万円(平均月収約11万円)、インドネシアは約24万~38万円(平均月収約2.9万円)と定めた。そもそも、東・東南アジアにおいては相続税がほぼゼロパーセントに等しい。つまり、お金持ちは何世代にも渡り一生お金持ちで、その逆も言えるということなのだ。そのため、日経企業が東・東南アジアへ進出するにあたって、これらの層以上にアプローチする必要があるが、彼らのメディア行動としては、「高い情報収集能力」と、集めた情報の周囲への「お裾分け」が得意な傾向がある。それゆえ、消費財を販売するにあたって、いかに製品に対しての信頼を醸成するかが重要であり、芸能人やKOL(Key Opinion Leader)による口コミや、各種有名メディアとの連携、またFacebookやECモール上でもコメントがあれば即レスすることなど、当たり前のような誠実さが重要になってくるのである。
〇エリアマーケティングの可能性
上記の貧富の差の話は、エリアマーケティングにも繋がってくる。日本と違い東南アジアでは富裕層と非富裕層では住む場所はもとより生活圏も異なってくる。私がバンコクに住んでいて驚いたのは、ある高級ホテルに少し褐色の肌の方が入られた際に、周りの方がジロジロと見ており、最終的には警備員に止められていたのを思い出す(タイでは肌が白いことがハイステータスの要素だったりする)。これは人間関係にも言えることで、富裕層と中間層以下が行動を共にすることはあまりないのだ。一方でこれは我々広告会社にとってはチャンスでもあって、「新興富裕層」以上の方がいるエリアは限定されるため、OOHやポップアップストアの出店が日本以上に効果があったり、また車が日本の2~3倍の金額となることもあり、中間層以下は運転できないため、意外にもラジオ広告の費用対効果が高かったなどという声も耳にしたりする。
〇インバウンドへの期待
ここ10年以内でバンコクや台湾に住んでいて感じたこととして、残念なことに「日本への憧れ離れ」を痛感する。コスメであれば圧倒的に”韓国”だし、健康食品でも自国の安い商品の購入が多いと感じる。昨今では、円安の影響でアジアの方々の訪日機会が増えているが、私はそこに非常に可能性を感じている。日本に来てもらい、改めて日本の食や文化、また四季の体感によって日本を好きになってもらいたい。それが逆流して、アジア現地でも改めて日本製商品への憧れが再燃し、購入意欲がより高まってくれることを期待したい。


引用:https://ameblo.jp/masasige1616/entry-12659424651.html