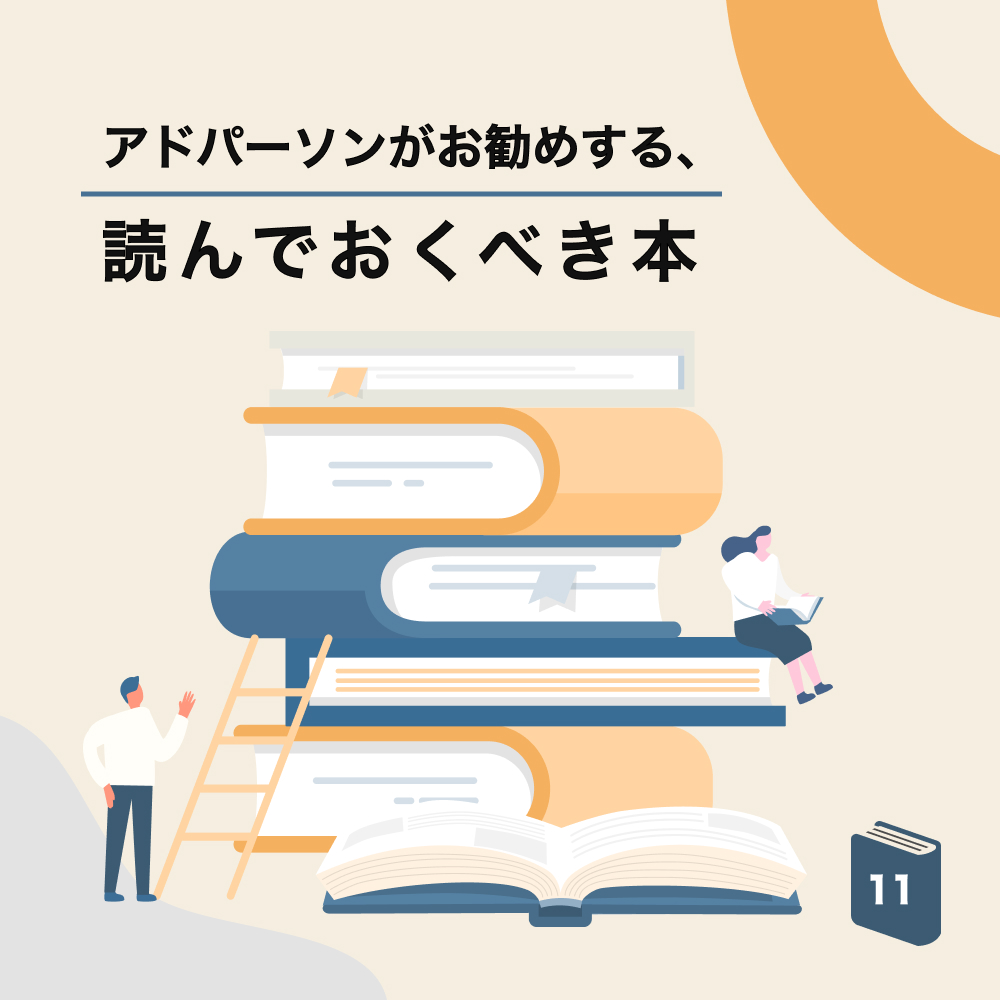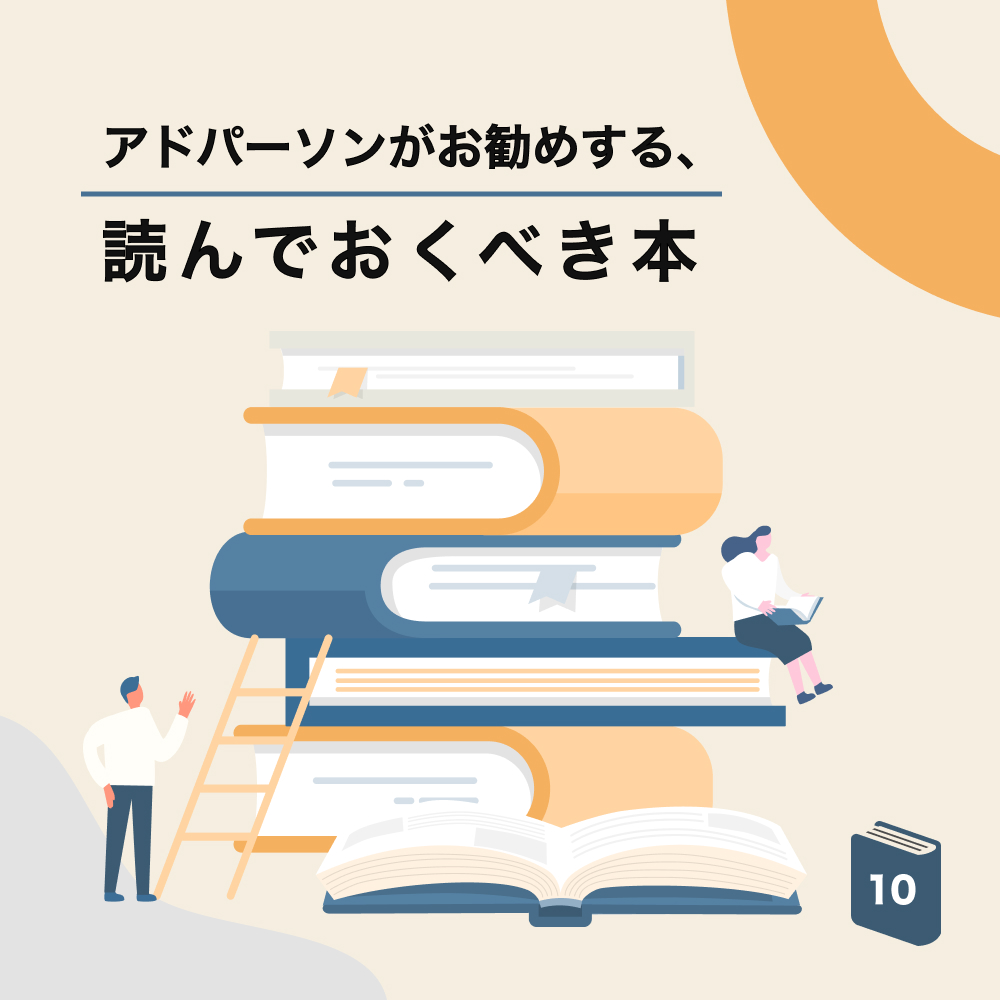ソリューションユニット フェロー/
ひと研究所 所長
2009年ビデオリサーチ入社。広告会社や広告主をクライアントとしたリサーチの企画・分析部門や、若者研究チーム参加を経て「ひと研究所」に参画し、 2024年より現職。「生活者のメディア行動」をテーマに研究・発信活動を行いながら、クライアント個別課題の調査実施・分析に携わる。修士(社会学)、専門社会調査士。
筆者は1984年生まれで、中学生のころにPCでインターネットを利用し始め、高校生で携帯電話を持ち、大学生のころにSNSが登場、就職後にスマートフォンが普及した世代です。
若い世代で起きつつある情報意識の変革
■メディアの体験の世代間ギャップ
筆者は1984年生まれで、中学生のころにPCでインターネットを利用し始め、高校生で携帯電話を持ち、大学生のころにSNSが登場、就職後にスマートフォンが普及した世代です。先日、筆者はある大学の講義に登壇したのですが、受講生の多くは2004年生まれで、中学生のころからスマートフォンを持ち、SNSやネット動画もそのころから使い始めた世代でした。このようなメディア体験の世代間ギャップは、情報に対する意識にも違いを生む可能性が大いにあります。今回は、この点を検証した分析結果をご紹介します。
■若い世代で見られる“情報意識”の変化
情報意識の変化を探るため、「情報収集に熱心なほう」「情報収集は自ら積極的におこなうほうだ」「興味関心ごとの蘊蓄を持っている」「最新の情報はいち早く入手したいほうだ」をピックアップし、関東在住の15~69歳男女、15~19歳男女、20~24歳男女のデータを見てみます(図1)。
時系列では15~69歳は上昇傾向が確認でき、この10年で情報収集に積極的で深く知るようになってきている傾向が読み取れます。一方で、若年層(15~19歳、20~24歳)のグラフは全体の傾向とは必ずしも一致しておらず、横ばい傾向が見られます。ここから、若い世代ほど意識の傾向が異なってきている可能性がうかがえます。

(ACR/ex 東京50km圏 2014年4-6月~2024年4-6月調査)
そこで、世代の違いの影響を検証するために、「コウホート分析」を用いて、各世代が持つ意識特性を分析しました。詳細な方法論は割愛しますが、情報意識項目について、「時代効果」(その時々の社会全体による影響)、「年齢効果」(その時々のその人の年齢やライフステージによる影響)、「世代効果」(その人の生まれ年と、子供のころの経験による影響)の3つの要素に分解する手法です(図2)。

分析の結果、1999年生まれまでの世代では下の世代になるほど情報意識が上昇していますが、2000年生まれ以降の世代では下降に転じています(図3)。つまり、2000年生まれ以降の世代では、いずれの情報意識も弱まってきていることになります。

※横軸は世代(生まれ年ごとに5歳ごとに区分)
■情報・コンテンツがあふれる世代の意識
コウホート分析の結果、若い世代は情報を積極的に収集したり、深く知ろうとしたりする態度が弱くなっていることが分かりました。この変化の背景には、冒頭に触れたように、彼らが10代のころからスマートフォンを持ち、SNSやネット動画を利用することも当たり前で育ったことが影響していると推察できます。
SNS普及以前、インターネットで情報収集するためには、検索エンジンで文字列を検索することが主流でした。いわば、能動的な情報収集です。しかし、SNSにおける「タイムライン」やネット動画における「おすすめ機能」は、興味関心のある情報やコンテンツを次々と手元のスマートフォンに届けてくれます。つまり、検索行動をしなくとも情報やコンテンツを得られる状態です。若い世代は、10代のころからこのような環境を体験し続けてきている結果、積極的に情報を集める必要性を感じにくくなっていると考えられます。スマートフォンとネットサービスが作る情報環境に適合した結果、上の世代とは異なる、いわば「情報意識の変革」が起きている可能性があります。
もちろん実際には、若い世代はあふれるくらいの情報・コンテンツに接していると考えられます。むしろ、日常的に大量の情報に接しているからこそ、“情報を集める”という行為を意識する必要がなくなっているのかもしれません。そして、このような人々の中には、あふれる情報・コンテンツの取捨選択・フィルタリングのために「インフルエンサー」や「推し」といった“自分の信頼できる特定の人物や物事”を起点・きっかけとして情報接触する傾向もみられます。企業は今後、現在の若い世代の持つこのような情報意識や情報接触の特徴を前提とし、効果的なコミュニケーション施策を実施していく必要があることを示唆した結果といえます。
今回は若い世代の情報意識の変化というお話をしましたが、次回は、シニア層にフォーカスをして意識変化を見ていきたいと思います。