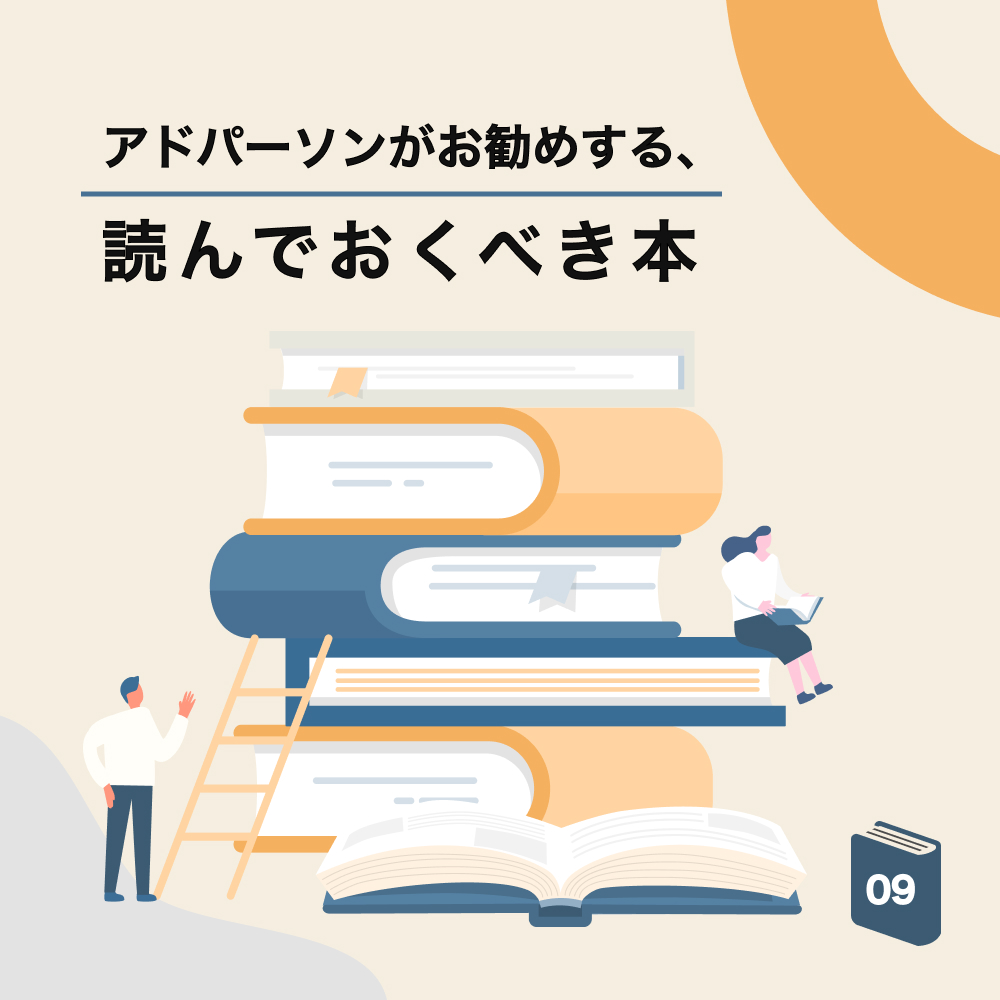DXコンサルティング本部DXコンサルティング局
チーフAIストラテジスト
大手コンサルティングファーム、クリエイティブ系法人向けスタートアップを経て、現職。メディア、Webサービス、通信、エネルギー業界を中心に、DX企画、AI実装、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。 コンサルティング活動の傍ら、社内DX部門にて外部情報発信やAI系スタートアップとの協業に従事。クリエイティブ系法人向けSaaS企業にてCustomer Successを立上げ、契約更新率の大幅改善を達成。新規プロダクトの立ち上げ等も主導。現職においてはDXコンサルティング事業/組織の立ち上げを主導しながら、プロジェクトリード、及び、ブランディング/マーケティング活動に従事。また、博報堂DYグループでAI活用を進めるHCAI Instituteへ所属。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)。
AI活用の熱狂が続く2025年。この連載では、技術論ではなく「AIをいかに組織に浸透させるか」を論じてきた。前回は、AIユースケースを構造的に理解し戦略的に活用を進める羅針盤として、「AIユースケース5段階モデル」を提示した。
第4回 AI人材育成の設計図 ~いまAI活用組織に求められるケイパビリティとは?~
AI活用の熱狂が続く2025年。この連載では、技術論ではなく「AIをいかに組織に浸透させるか」を論じてきた。
前回は、AIユースケースを構造的に理解し戦略的に活用を進める羅針盤として、「AIユースケース5段階モデル」を提示した。

本稿では、この5段階モデルが、単なるユースケース開発方針に留まらず、AI人材開発や組織設計においても、強力な設計図となり得ることを示したい。
これから自組織のAI活用を進めたいと考えている経営層、組織長、またはAI活用推進者にとっては、きっと関心事と合うはずだ。
ユースケースレベルと求められるケイパビリティの連動
さて、AIユースケースの5段階モデルをおさらいすると、以下の通りであった。
- レベル1:チャットでの直接利用
- レベル2:プロンプト・カタログ利用
- レベル3:カスタムAIボット利用
- レベル4:簡易ツール・EUC利用
- レベル5:業務ソリューション・システム組込
これらの各レベルの実現に向けて求められる人材のケイパビリティは大きく異なる。この点を理解することが、AI人材育成戦略の第一歩だ。
いきなりではあるが、5段階モデルに紐づくケイパビリティの一覧は、以下の図を確認してほしい。その上で、レベルごとに重要な点を補足していく。

レベル1:チャットでの直接利用に向けて ― 「対話の継続」と「利用の習慣化」が鍵
最も手軽なこのレベルでは、特別な専門スキルはほぼ不要だ。
しかし、AIとの対話、いわゆる「ラリー型」でAIと会話しながら欲しい情報にたどり着く発想が重要となる。一問一答で終わらず、対話を重ねてAIの能力を引き出すスキルが求められる。
また、見落とされがちだがさらに重要なのは「利用の習慣化」だ。日常業務のパートナーとしてAIを活用する行動習慣とそれを推奨する文化醸成を仕掛けることが、活用浸透の土台となる。
レベル2:プロンプト・カタログ利用 ― 「プロンプトエンジニアリング」と「成果物の定義」が真価を問う
フォーマット化されたプロンプトを活用し、質の高いアウトプットを目指すこのレベル。
よく話題となるプロンプト作成技術(プロンプトエンジニアリング)についても、一定求められるようになる。しかしながら、単なるプロンプト作成技術以上に、「このタスクでは、どのようなアウトプットが得られれば成功か」という成果物の設計を明確にする能力、そしてその定義に基づきプロンプトのPDCAサイクルを回す実践力が問われる。
この成果物の設計力と、それに向けたPDCAの実践力は、レベル3以降のユースケースで本格化する業務改善(BPR)の活動の基礎スキルにもつながる。
レベル3:カスタムAIボット利用 ― 「AIシステムの構造理解」を深める
GPTsやGemのようなカスタムAIボットの利用は、特定の業務や作業に特化したAIツールを創ることを可能にする。基本的にはノーコードで実現可能であるため、エンジニアリング知識は求められない。
それでもこのAIボット作成の経験は、「AIシステムがどう機能するのか」という構造的理解が必要となる。AIを制御可能な「ツール」として業務に組み込む感覚がここで養われる。
レベル4:簡易ツール・EUC利用 ― 「エンジニアリング」と「業務変革力」の萌芽
レベル3までのチャットインターフェースの制約を超え、様々な業務ツール開発が中心となる。ローコード/ノーコードとはいえ、必然的にエンジニアリングスキルが必要となる。
また、きちんとAIツール使って業務を変革するためには、既存業務プロセスの理解とToBe像の設計、つまり業務要件定義の能力や時には業務プロセス自体を再設計するBPR的視点も求められる。
このようなエンジニアリングを行うメンバーと、業務要件策定やBPRを行うメンバーは、別の人が担い、チームワークで開発することも多い。つまり、レベル4以上において求められるケイパビリティは一人で保有することを求める必要は必ずしもない。あくまで組織全体、もしくは外部パートナーを含めた保有を考えるケイパビリティ調達戦略が求められる。
レベル5:業務ソリューション・システム組込 ― 「本格的な開発力」と「プロジェクト推進力」
AI機能が本格的な業務システムに組み込まれる最終段階。高度な「システム開発能力」や「プロジェクトマネジメントスキル」が不可欠だ。
大規模システム開発では、複数チーム統括、複雑な要件整理、納期・品質・コスト管理能力が求められる。エンドユーザー業務部門と開発エンジニアチーム間の「壁」を乗り越えるブリッジング能力も極めて重要となる。
組織的な人材育成戦略の羅針盤として
このように、AIユースケースの5段階モデルは、各レベルで求められる人材のケイパビリティを明確に示す。
今、このようなケイパビリティのリストをもとに、多くの企業で議論されているのは、
「自組織はどのレベルのAI活用を目指すか?」
「そのためには、どのレベルのケイパビリティを持つ人材を、どれくらいの規模で抱えるべきだろう?」
「そのような人材をどのように育成・調達すべきか?」という問いだ。
また、これに答えるためには、まず現状の人材のケイパビリティを正しく把握することが肝要だ。現状把握のために「アセスメント」を第一歩とする手も有効と考えられる。5段階モデルを共通言語とし、個々の従業員の強みや育成ポイントを可視化することから始めることもおすすめしたい。研修やワークショップを行い、そこで合わせて簡易な人材アセスメントを行うケースも多い。
次回は、この5段階モデルをさらに組織論へと接続し、AI活用推進のための具体的な体制構築やスキル開発プログラムについて深掘りする。ぜひ、引き続き注目してほしい。