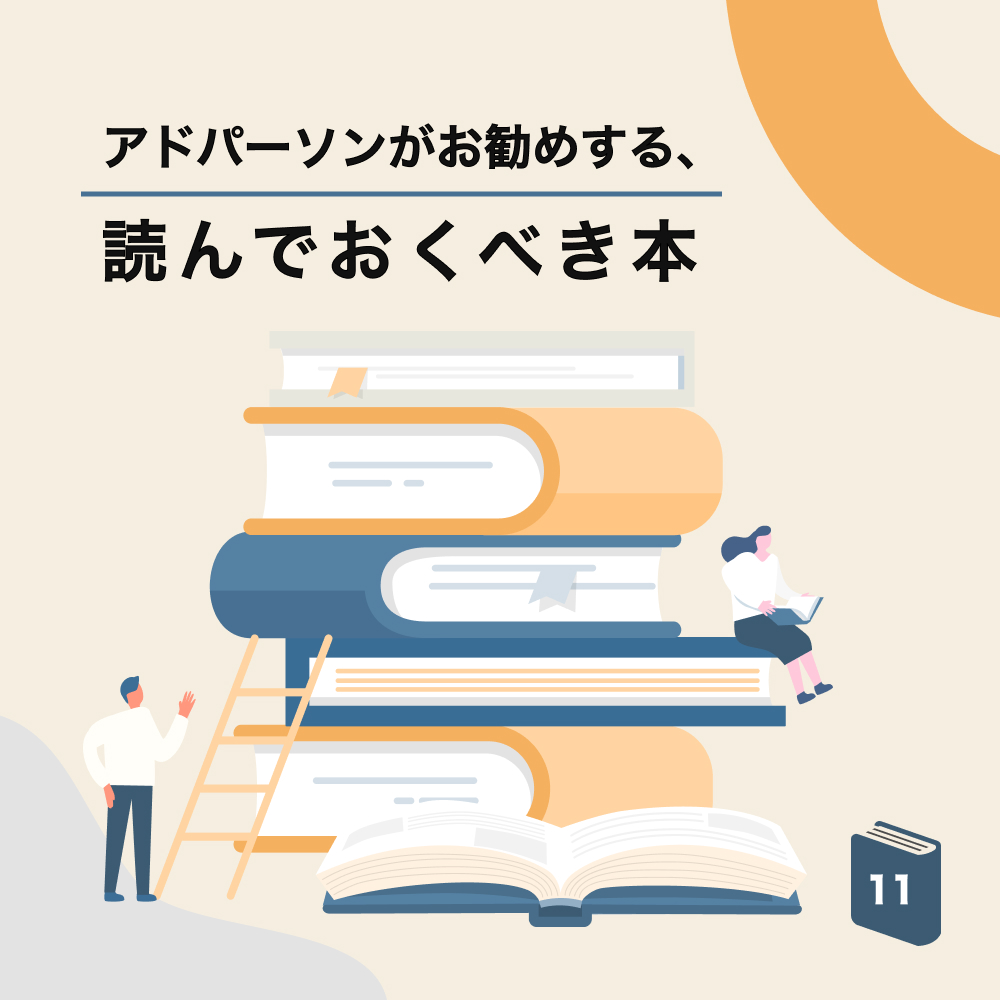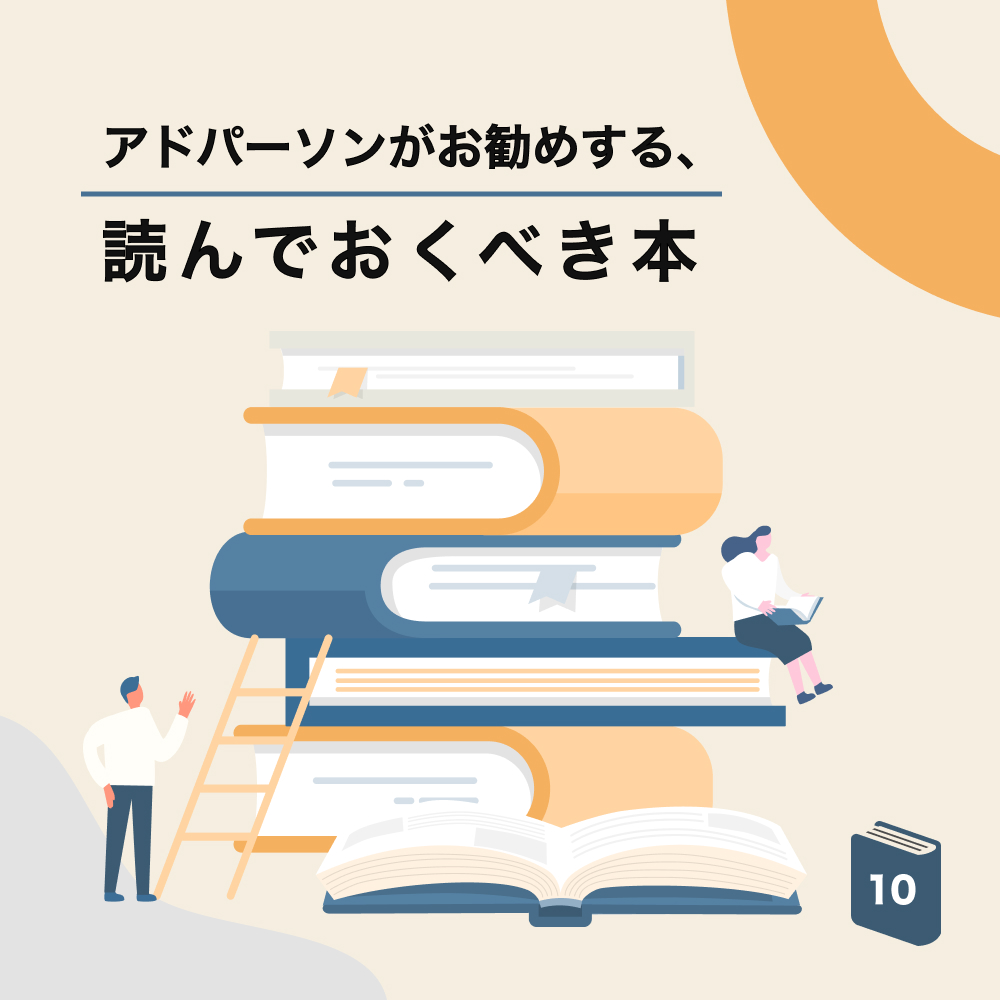テレビ・メディアコンテンツユニット
エグゼクティブプロデューサー(ひと研究所 主任研究員)
2000年ビデオリサーチ入社。国際事業部門、日本コンテンツ海外チャンネル出向を経て、2018年より現職。現在は大規模生活者プロフィールデータ(ACR/ex)の事業統括並びにメディア・コンテンツ・バリュー指標開発に従事。
私たちの情報との付き合い方は、この十数年で大きく変わりました。かつてはテレビやラジオから一方的に“受け取る”のが当たり前だった情報も、今ではスマートフォンやパソコンを使って“自分から選んで取りに行く”時代になっており、メディアとの関係性は、より自由に、そして多様になっています。
~生活者の「メディア」へのアプローチ変化とその印象~
■「選べる時代」~メディアとのちょうどいい距離感~
私たちの情報との付き合い方は、この十数年で大きく変わりました。かつてはテレビやラジオから一方的に“受け取る”のが当たり前だった情報も、今ではスマートフォンやパソコンを使って“自分から選んで取りに行く”時代になっており、メディアとの関係性は、より自由に、そして多様になっています。
2024年のメディア消費時間の推移で1日あたりの平均利用時間は、テレビが116分、インターネット(PCやスマートフォンなど)が117分と、ほぼ同じくらいの時間が費やされています。ネットの時代と言われる中でも、テレビは依然として人々の暮らしに深く根づいており、変わらぬ存在感を放っています。
また、テレビの視聴スタイルにも変化が見られます。録画再生(23分)やCTV(コネクテッドTV/17分)といった、時間や場所にとらわれない新しい楽しみ方が広がってきました。「その時間に見るもの」だったテレビが、「好きなときに楽しめるコンテンツ」として再評価されているのです。
また、ゲームも1日あたり23分と、他のメディアに比べても高い利用時間を記録しています。かつては子ども向けの娯楽と見られがちだったゲームも、いまでは世代を問わず楽しめる趣味のひとつとして、すっかり生活の一部となっている様子がうかがえます。
どのメディアにもそれぞれの魅力があり、家族でテレビを楽しむ日があれば、ラジオを聴きながら仕事をする日もあります。インターネットで情報を調べたり、ゲームでリフレッシュしたり、新聞で世の中の動向を把握し、雑誌で趣味の世界に浸る時間を楽しんだりと、豊富な選択肢の中で自分に合ったメディアと心地よく向き合うスタイルが定着してきていることが見て取れます。

■生活者の印象から見る“お役立ち”メディアとは
次に、2024年の最新データをもとに、各メディアが持つ「信頼性」「話題性」「娯楽性」「利便性」といった印象についてご紹介します。
まず、地上波民放テレビについては、「生活に役立つ」と感じている人が41.6%と最も多く、次いで「人気や流行を知るのに役立つ」(39.8%)、「趣味に役立つ」(34.1%)といった項目が上位に挙がっています。また、「接していて楽しい」という回答も33.3%にのぼり、テレビが情報源であると同時に、エンターテインメントとしても高く評価されていることがうかがえます。
ラジオに関しては、「接していて楽しい」(11.9%)が最も多く、次いで「生活に役立つ」(10.3%)、「趣味に役立つ」(10.2%)という印象が上位にランクインしています。ラジオ特有の心地よさや、"ながら聴き"といったライフスタイルに自然に溶け込むスタイルが支持されている様子が見受けられます。
新聞は、「生活に役立つ」(19.2%)に加え、「情報に信頼性がある」(17.6%)という印象が強く、インターネットでの情報収集が日常的な今でも、新聞の“信頼性”は依然として大きな価値を持っているといえます。
雑誌は「趣味に役立つ」(21.9%)という点で特に評価されており、特定の関心や嗜好に応えるメディアとしての強みが現れています。
口コミに関しては、「生活に役立つ」(19.1%)や「接していて楽しい」(16.9%)といった印象が上位を占めており、日常生活に密着したリアルな声が有益で親しみやすい情報源として捉えられている状況です。
ブログやSNSは、「人気や流行を知るのに役立つ」(23.4%)という点で最も多く評価されています。トレンドの把握に欠かせない存在であることがうかがえます。また、「生活に役立つ」や「趣味に役立つ」といった実用性も高く評価されています。
このように、各メディアにはそれぞれ異なる強みと特徴があり、生活者はそれを上手に使い分けていることがわかります。

今回は、2000年以降のメディア接触行動の変化と、生活者におけるメディアの印象についてご紹介しました。次回は、情報取得のみならず実用性の印象も高まっている「SNS」について、世代別の潮流をご紹介いたします。