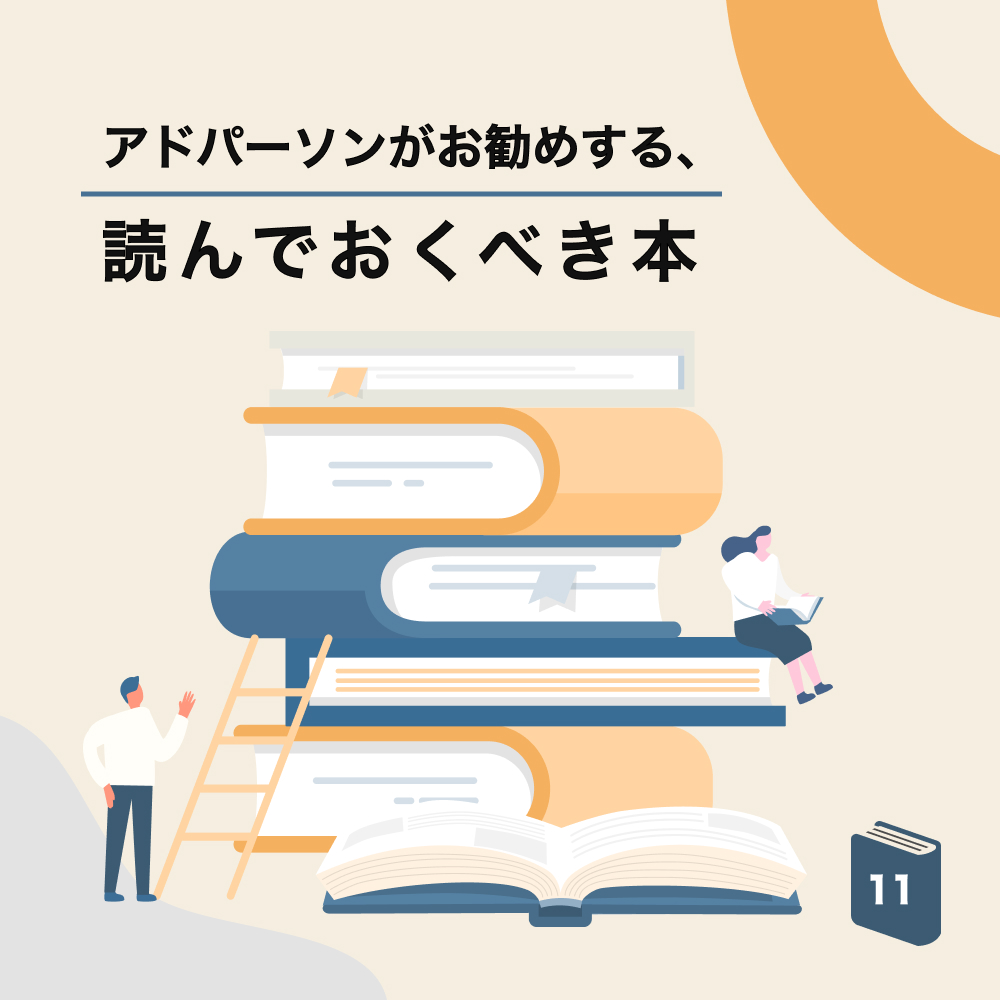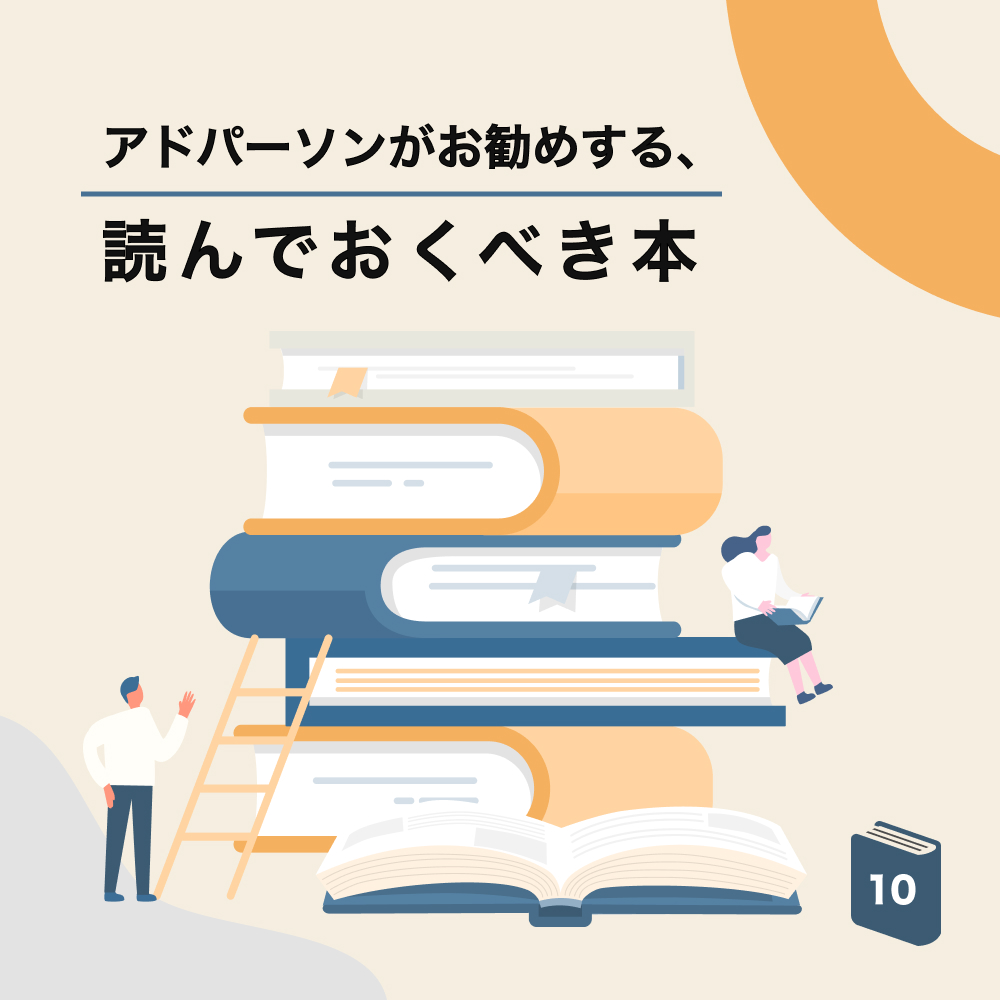テレビグループ
グループマネージャー
2000年ビデオリサーチ入社。
調査部門、営業部門、サービス開発部門、JIAA出向を経て、2022年より現職。現在はテレビ視聴率事業の統括並びにテレビ・動画関連サービス開発に従事。
私が入社した2000年当時、テレビは娯楽のど真ん中に位置付けられていて、誰もが好きな番組の放送を待ちわびていたものです。視聴率(世帯視聴率)も好調で、今ではなかなか見られない30%超えの番組がいくつも存在しました。
~テレビメディアからみた視聴行動の変化~
■16/30が示すテレビメディアの存在感
私が入社した2000年当時、テレビは娯楽のど真ん中に位置付けられていて、誰もが好きな番組の放送を待ちわびていたものです。視聴率(世帯視聴率)も好調で、今ではなかなか見られない30%超えの番組がいくつも存在しました。(※図1参照)。プロ野球やオリンピックなどのスポーツコンテンツは当たり前のように高視聴率を連発し、連続ドラマやレギュラーバラエティであっても20%を超える視聴率をたたき出していました。テレビは圧倒的な人気と実力を兼ね備えた力強いメディアであり、放送局の切磋琢磨によって、良質な番組が次から次へと生み出されることになりました。この時点で視聴率は“世帯“が基準であったことからも、当時の生活者にとって自宅におけるテレビメディアの存在感や役割というのは大きなものであったことを伺い知ることが出来ます。
■個人視聴への変化とタイムシフト視聴率
魅力ある番組が沢山あることで、視聴者にとって番組選択は大きな悩み事となりました。放送局はテレビメディアの存在感が大きくなる中で、F1、M1といった世帯内の若い世代を狙った番組を制作するなど、個人視聴率も意識するようになります。その結果、家族それぞれで見たい番組が異なるようになり、世帯内でのチャンネル争いも過熱します。テレビのチャンネルをどの放送局に合わせるかが家族との争いに繋がることなど、今の視聴者にとっては信じられないことかもしれませんが、これは実際に多くの世帯で起きていた実話なのです。
その争いを解決すべく、手軽に大量の番組を録画できる機器が世に現れました。
記録用ハードディスクを内蔵したHDDレコーダーの登場です。
リアルタイムで見ることが出来るのは1番組だけですが、録画することで見たい番組を全部見ることが出来ますし、何度も繰り返し見ることが出来ます。また、家族とのチャンネル争いを避けることもでき、一石三鳥の大活躍を果たします。
これがタイムシフト視聴拡大の大きなきっかけとなりました。
今すぐに見たい番組はリアルタイムで、後々繰り返し見たいものはタイムシフトでといったテレビ番組の見られ方に変化が生じており、現在の視聴経路の多様化はこの時から始まっていたことになります。
このような視聴方法の変化を捉えるべく、2016年10月にビデオリサーチが関東地区でタイムシフト視聴率の測定を開始し、その実態把握に乗り出します。測定開始以降、タイムシフト視聴行動は増加傾向を示しており、視聴者に好きな番組を好きな時間に楽しむ生活スタイルが定着しつつあることが明らかになりました。
また、個人視聴への変化に伴い全国でその実態を把握するため、2020年4月に視聴率調査の仕様変更が行われます。全ての調査地区で機械式個人視聴率が開始となり、全地区でタイムシフト視聴率の提供が開始されるとともに、全国の視聴人数を把握することが可能になりました。
図2)2017年 年間高タイムシフト視聴率番組20(関東地区)
図3)2020/03/30(月)~12月31日(木) 全国平均推計視聴人数上位20番組
■コロナ禍を経て変化するメディア環境と視聴行動
ところが、2020年~2022年にかけて世界的に流行したコロナウイルスが、テレビ視聴スタイルを激変させます。コロナ感染拡大が進む中、緊急事態宣言発令されたことで自粛生活が浸透しました。在宅ワークの推進とともに東京オリンピックをはじめ数々のイベントが中止、巣ごもり生活が始まりました。番組編成への影響も大きく、放送が一時中断された番組があったり、再放送や再編成番組に代わるなど大幅な変更を余儀なくされたことで、テレビデバイスの使われ方に変化が起きます。
既にYouTubeやNetFlix、TVerなどの動画配信サービスが勢いを見せていましたが、テレビデバイスのインターネット接続率上昇に伴い、配信動画視聴が自宅内視聴行動の有力な選択肢となりました。いわゆるコネクテッドTV(CTV)での配信動画視聴の拡大はテレビデバイスの使われ方を多様化させることになります。その実態把握に向け、ビデオリサーチでは、2024年4月より、自宅内の動画配信プラットフォームの利用を捕捉するサービスの開始に至ったのです。
その詳細はまた別の機会に触れさせていただきますが、今回は2000年以降のメディア接触行動の変化を、テレビを例に述べさせていただきました。今後、本連載ではメディア環境の変化とそれに伴う視聴者のメディアに対する意識や接触行動の移り変わりについて、メディア視点と生活者視点の両面から明らかにしていきたいと思います。