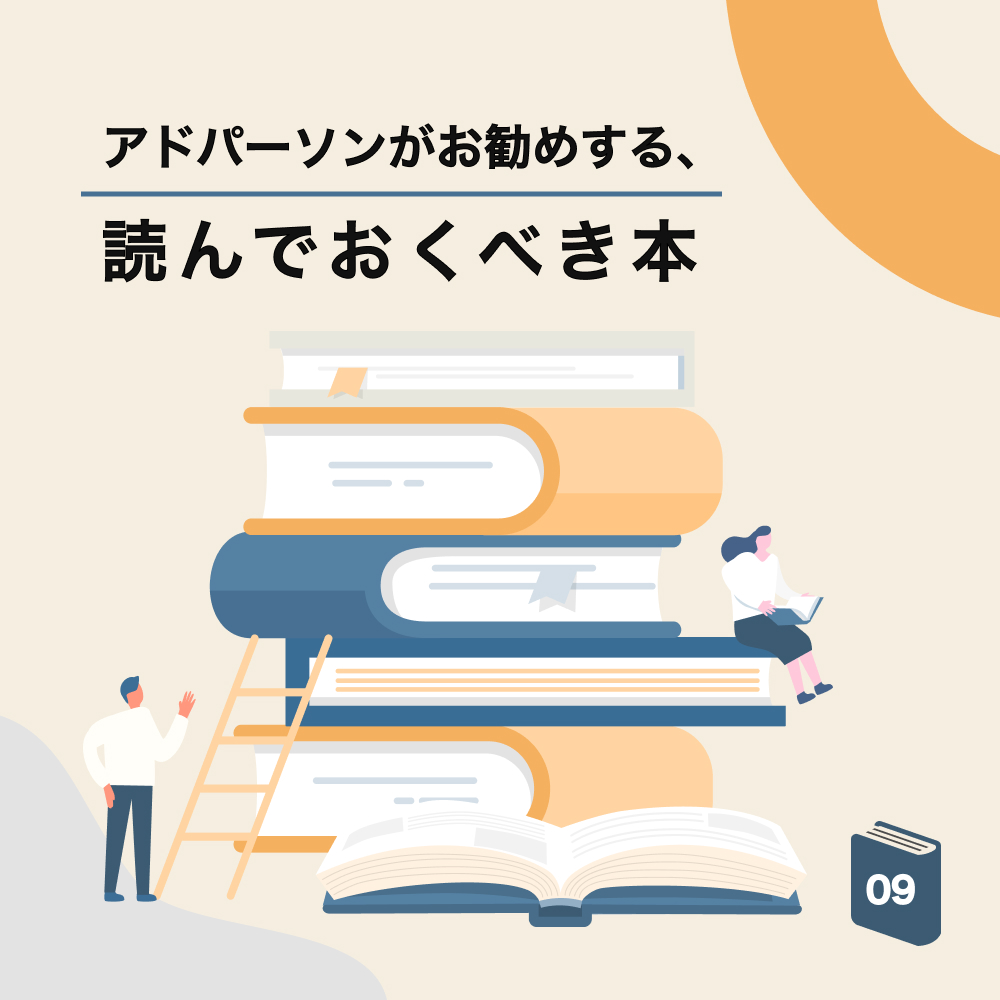DXコンサルティング本部DXコンサルティング局
チーフAIストラテジスト
大手コンサルティングファーム、クリエイティブ系法人向けスタートアップを経て、現職。メディア、Webサービス、通信、エネルギー業界を中心に、DX企画、AI実装、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。 コンサルティング活動の傍ら、社内DX部門にて外部情報発信やAI系スタートアップとの協業に従事。クリエイティブ系法人向けSaaS企業にてCustomer Successを立上げ、契約更新率の大幅改善を達成。新規プロダクトの立ち上げ等も主導。現職においてはDXコンサルティング事業/組織の立ち上げを主導しながら、プロジェクトリード、及び、ブランディング/マーケティング活動に従事。また、博報堂DYグループでAI活用を進めるHCAI Instituteへ所属。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)。
本連載も6回目を迎えた。前回は、AI活用が一部の先進層にとどまり、組織全体に広がらない課題について論じた。そして、壁を越えるための武器として、社内の従業員を「顧客」とみなし、その心を動かすインナーマーケティングの重要性を論じた。
第6回 AI活用推進の起点 を探す―「センターピン」は誰だ?
本連載も6回目を迎えた。
前回は、AI活用が一部の先進層にとどまり、組織全体に広がらない課題について論じた。
そして、壁を越えるための武器として、社内の従業員を「顧客」とみなし、その心を動かすインナーマーケティングの重要性を論じた。
今回は、その議論をさらに一歩深めたい。
AI活用を組織に浸透させるためにアプローチする際、「どの従業員セグメントから優先的に働きかけるべきか」という、より戦略的な問いに焦点を当てる。
全方位に画一的なアプローチをしても、組織は動かない。全体に最も影響を与え、そこを動かせば後は回転してまわりだすポイント ―いわゆる「センターピン」を見極める必要がある。リソースは常に限られているのだから。
全ての土台となる、経営層のコミットメント
本論に入る前に、大前提を確認しておきたい。
それは、経営層、すなわち役員クラスの強力なコミットメントが、AI活用推進の土台であるということだ。
彼らがAI共創の重要性を理解し、明確なビジョンを組織全体に発信すること。
そして、そのビジョンを実現するために必要な予算、人材、時間といったリソースを大胆に投資すること。
これなくして、いかなる組織変革も成功はおぼつかない。トップダウン型、ボトムアップ型いずれの組織であっても、明確な意思表示と支援体制があって初めて、組織は安心して新しい挑戦へと踏み出すことができる。この点は論を俟たない、絶対的な出発点と考えられる。
しかし、見落とされがちな真のセンターピン
経営層が力強い号令を発し、土壌を整えたとしても、それだけでは種は芽吹かない。
特に、汎用型AIアシスタント(ChatGPTやGemini Advanced、Copilotのように、各従業員に提供されるチャット型のAIツール)の利用促進においてはそれが顕著である。トップが描いた壮大なビジョンを、現場一人ひとりの日々の具体的な「行動」へと翻訳し、根付かせる役割が不可欠となる。
ここで光を当てるべきなのが、課長やチームリーダーといった「タスクマネジメント層」だ。彼らこそ、ともすれば見過ごされがちだが、実は最も重要なセンターピンである。
彼らは組織の戦略と現場のオペレーションを繋ぐ、結節点に位置しており、メンバーの日々の「タスク」を最も近い距離で管理・監督している存在である。AIの活用は、本質的にこの「タスク」そのものを変革する行為に他ならない。
思い出してほしい。彼らが普段、メンバーに対してどのようなコミュニケーションを取っているかを。
「A社の件、この観点でリサーチを進めておいて」
「B案の企画書、もう少し顧客のインサイトを深掘りできないか」
彼らの日々の指示の中にこそ、AIを組織の血肉に変えるチャンスが眠っている。例えば、先ほどの指示はこう言い換えられるだろう。
「A社の件、まずはAIで競合の動向を調べて、そのうえで深掘りするポイントを一緒に考えよう」
「B案の企画書、AIを使ってペルソナ分析をやり直したら、違うインサイトが見えるかもしれない。試してみないか?」
このように、日常のタスク指示の中に、AIの活用を自然に埋め込むこと。
この、具体的で実践的な「一言」を発することができるのは、日々の業務プロセスに責任を持つタスクマネジメント層だけなのだ。この役割は、個々のプロセスよりもさらに成果(アウトプット)に責任を持つ上位のマネジメント層では、担うことは難しい。
センターピンに求められる「実践力」と「見立て力」
では、この重要な役割を担うタスクマネジメント層には、いかなる能力が求められるのか。
彼らは単なるAIの「伝達役」では務まらない。少なくとも二つの重要なケイパビリティが必要だ。
一つは、彼ら自身の「活用力」だ。これは、自らがAIを日常的に使いこなす能力である。
情報収集や資料のドラフト作成はもちろん、企画の壁打ち相手としてアイデアを深めたり、複雑な思考を整理するためのパートナーとしてAIを使いこなす。その中で、AIの回答を鵜呑みにせず批判的に吟味する作法や、どのタスクをAIに任せ、どの部分を人間が担うべきかという戦略的な線引きを、自らの経験を通じて体得している状態だ。この実践的な知見なくして、具体的で説得力のある指示など出せるはずがない。
もう一つは、「マネジメント力」である。
これは、部下の業務プロセスを高い解像度で理解し、「その作業のこの部分は、AIで代替できる」「その分析は、AIを使えばもっと深く、速くできる」と、具体的な介入ポイントを発見して、伝えられる力だ。
例えば、部下が作成したアウトプットに対して「この部分はよく考えられているが、この調査観点の網羅性はAIを使えばもっと高められる」とフィードバックしたり、行き詰まっている部下には「それ、AIに相談してみたら?こういうプロンプトで聞くと、良いヒントがもらえるよ」と具体的な処方箋まで提示できる能力を指す。このマネジメント力によって、単なる作業効率化に留まらず、部下がより付加価値の高い業務に集中できる時間を生み出し、チーム全体の生産性を飛躍させることが可能となる。
タスクマネジメント層に狙いを定め、アンバサダーに引き上げる
ここまで述べれば、取るべき戦略は明確だろう。
全社一律のAI研修にリソースを投下するのではなく、まずはこの「タスクマネジメント層」に的を絞り、彼らを重点的に育成・支援することが重要だ。
ある企業では、この考え方に基づき「AI活用推進リーダー制度」、いわばアンバサダー制度を導入し、成果を上げている。
まず、各部署のタスクマネジメント層から、意欲や素質のある人材を推進リーダーとして選抜する。そして、彼らに対して、集中的なトレーニングやコーチングを実施し、AIの「活用力」と「マネジメント力」を徹底的に叩き込むのだ。
研修を修了したリーダーには、公式な「AI活用推進リーダー」の称号や、PCに貼るステッカーのような物理的なバッジを授与する。

こうした「可視化」が極めて重要だ。
称号やバッジは、本人に専門性への自覚とコミットメントを促す効果がある。同時に、周囲のメンバーにとっても「AIのことで困ったら、あの人に聞けばいい」という明確な目印となり、自発的な相談や学び合いを活性化させる。
ぜひ、あなたの組織における「センターピン」が誰なのか、この視点で見つめ直してほしい。