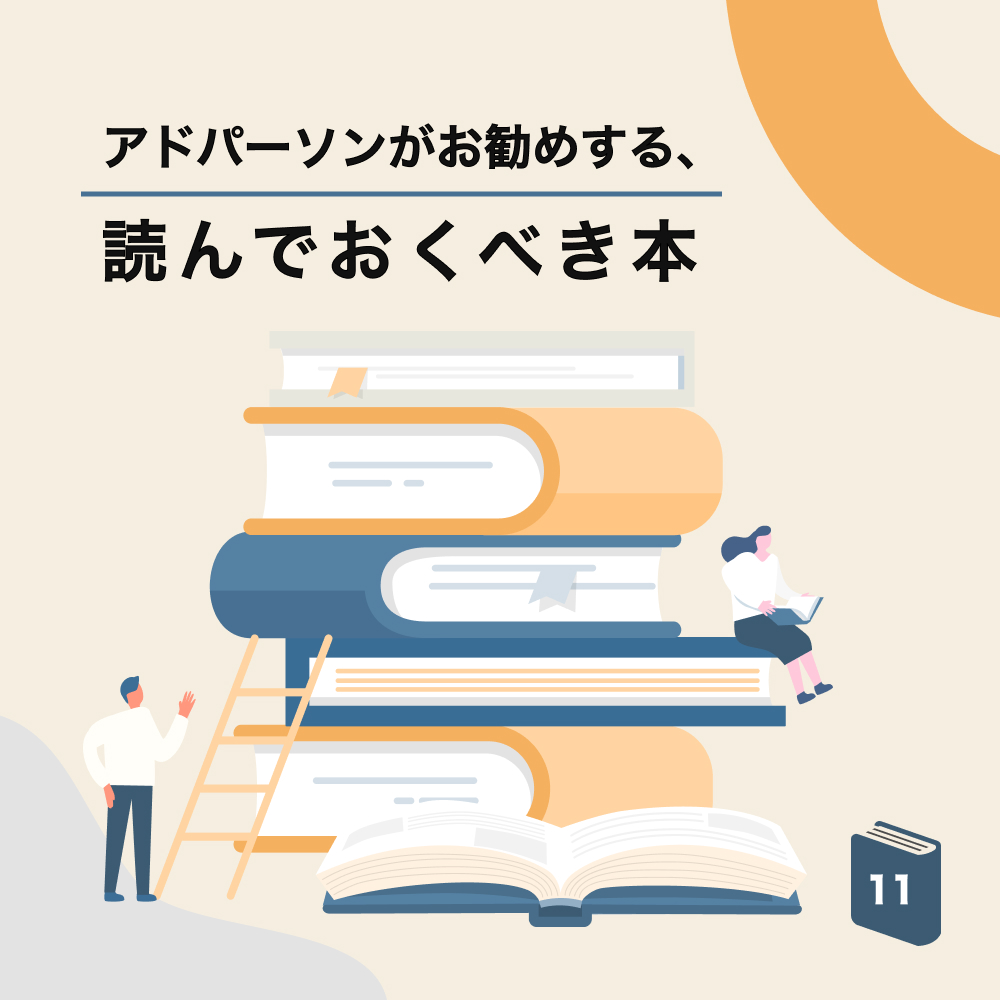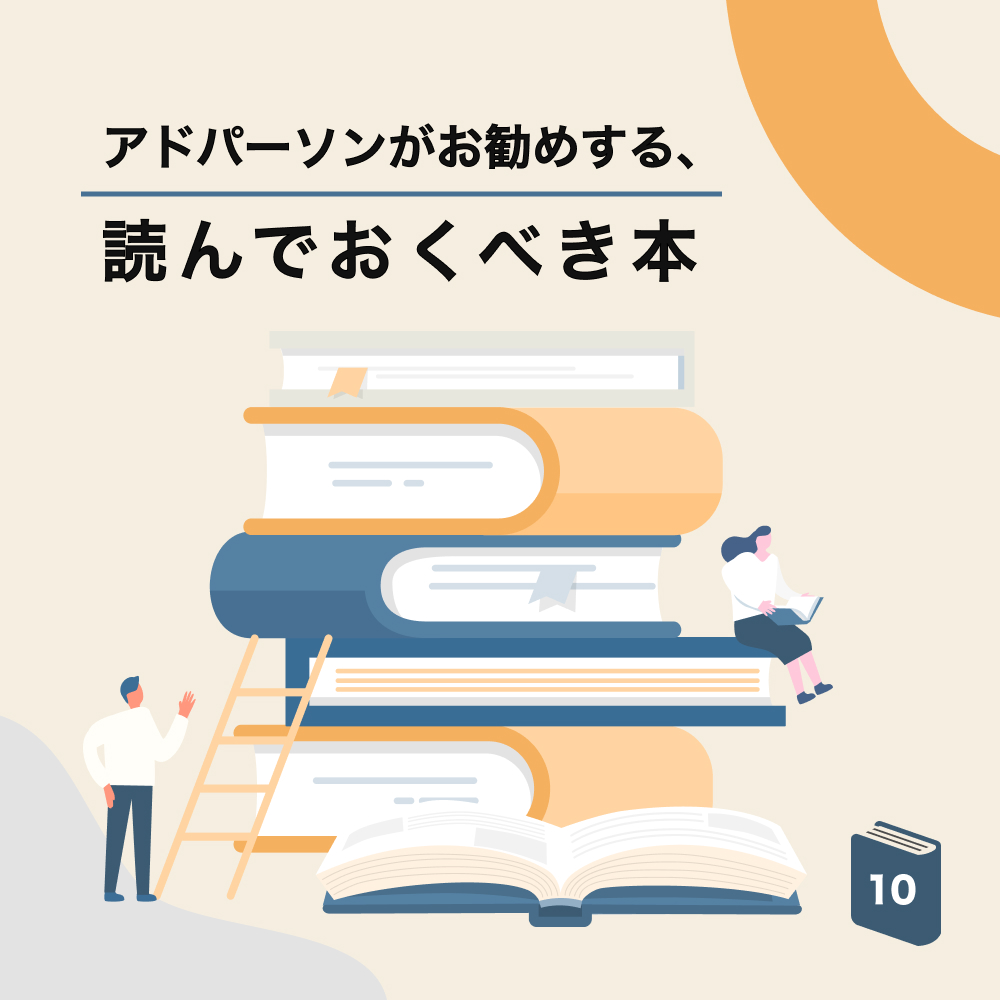マーケティング支援会社の営業として、そして生成AIが日常となった今、広告主のマーケティング活動に介在させていただいている意義を考えてみたい。
営業として向き合いたいこと
マーケティング支援会社の営業として、そして生成AIが日常となった今、
広告主のマーケティング活動に介在させていただいている意義を
考えてみたい。
広告はデジタルと非デジタルに分けられる。
デジタル広告の強みは明らか。計測・数値化でき、ターゲティング精度も
高く、スピーディで柔軟。
機械学習による最適化でROASを合わせ、施策の妥当性を示すことも可能。
広告予算配分の観点で、採用優先度が高いことは至極理にかなっている。
ただ、利点が明白が故に、同様の手法が数多く採用されているのも事実。
デジタル施策が当たり前となった今、そこにない別の価値こそ見出す
意義があると思う。
非デジタル領域における価値創出がその一つだと考える。
例えば駅の広告とスマホの広告。同じ商品なのに、印象が全然違う。
非デジタル施策は計測しづらいが、デジタルでは実現し得ない独自の価値が
あるように思う。
直接目で見て、手で触れられる。五感で体験できる。
モバイル上の検索行動に基づいているわけでもなく、レコメンドアルゴリズムの結果でもない「偶然性」による新たな出会い。
これらは、モノよりコト、機能的価値に加え情緒的価値が求められる
現在にあって、より大切な価値だと思う。
非デジタル施策により抱かれるブランドへの情緒的な印象は、
直接的な貢献度を計る難易度は高いが、CPA低下の一因となることも多い。
また長期的な財産としてブランドの価値に繋がってくると思う。
そんな非デジタル領域での価値をどう捉え、形にしていくかを考えることに
意義があると思う。
短期利益というミッションとは向き合いつつも、 一キャンペーンの個別最適化に終始せず、ブランドの長期的な価値向上を忘れずに、サービスの訴求軸の
深掘りやその見せ方の考案といったところを頑張っていきたい。
さらにデジタル・非デジタルという区分は、私たち業界の整理に過ぎず、
生活者にとっては触れるすべての接点が一つの体験として存在している。
支援会社として介在させていただくからには、効果を示しやすい
デジタル領域に加え、説明しづらい領域での価値を示し、
区分を超えたシームレスな生活者体験の価値最大化を目指していきたい。
難しいことではあるが、一営業として大切にしたい想いである。