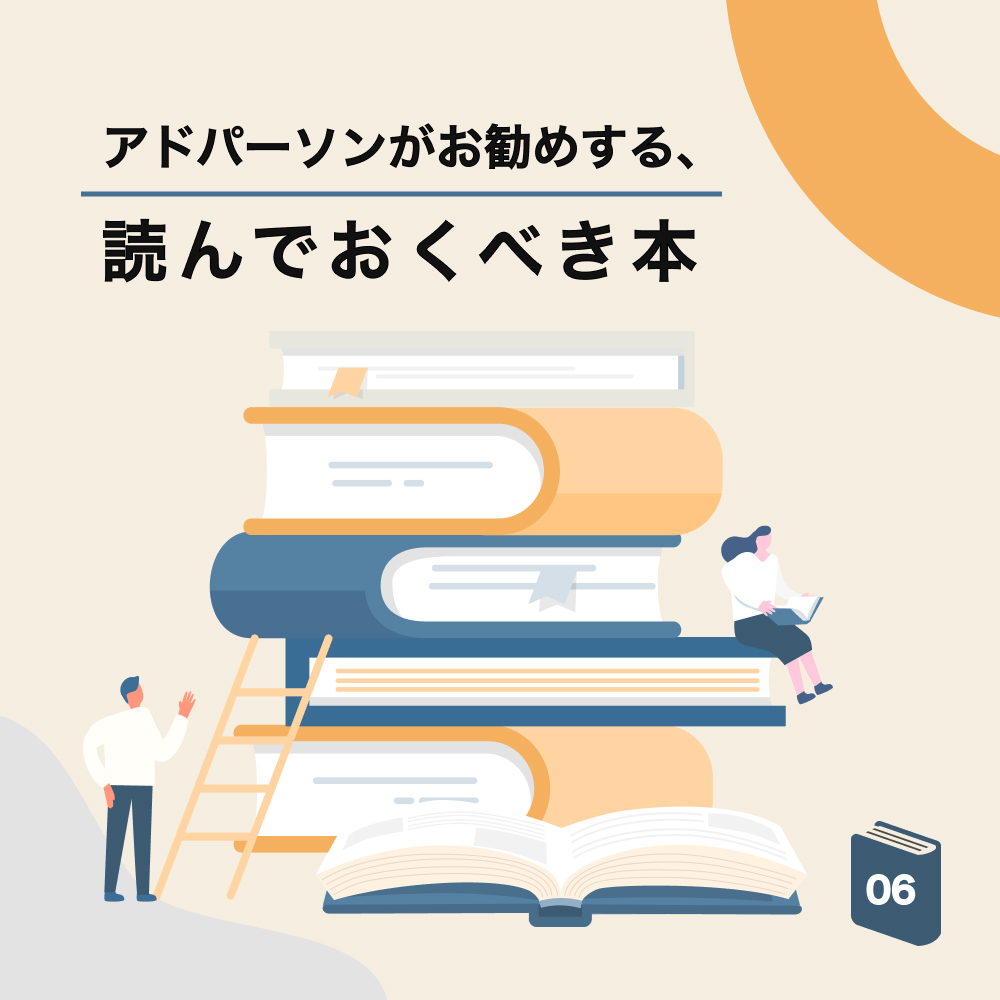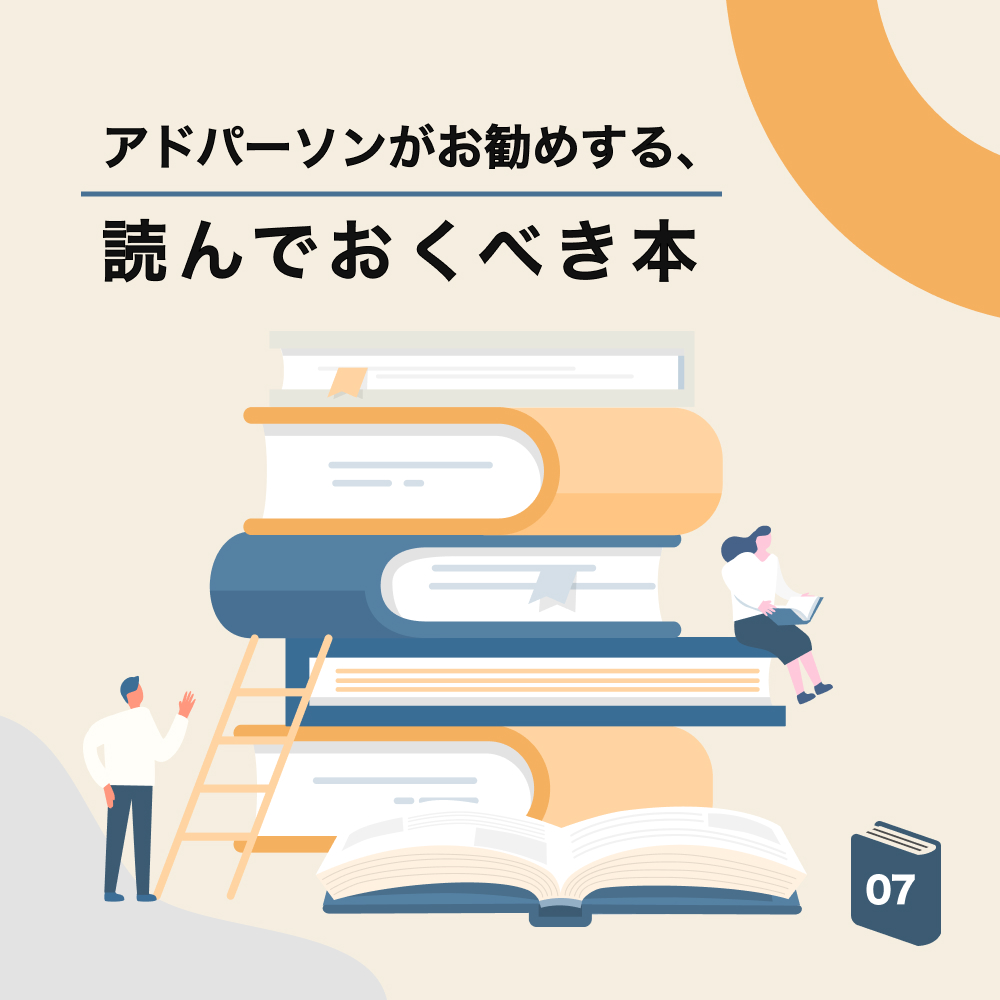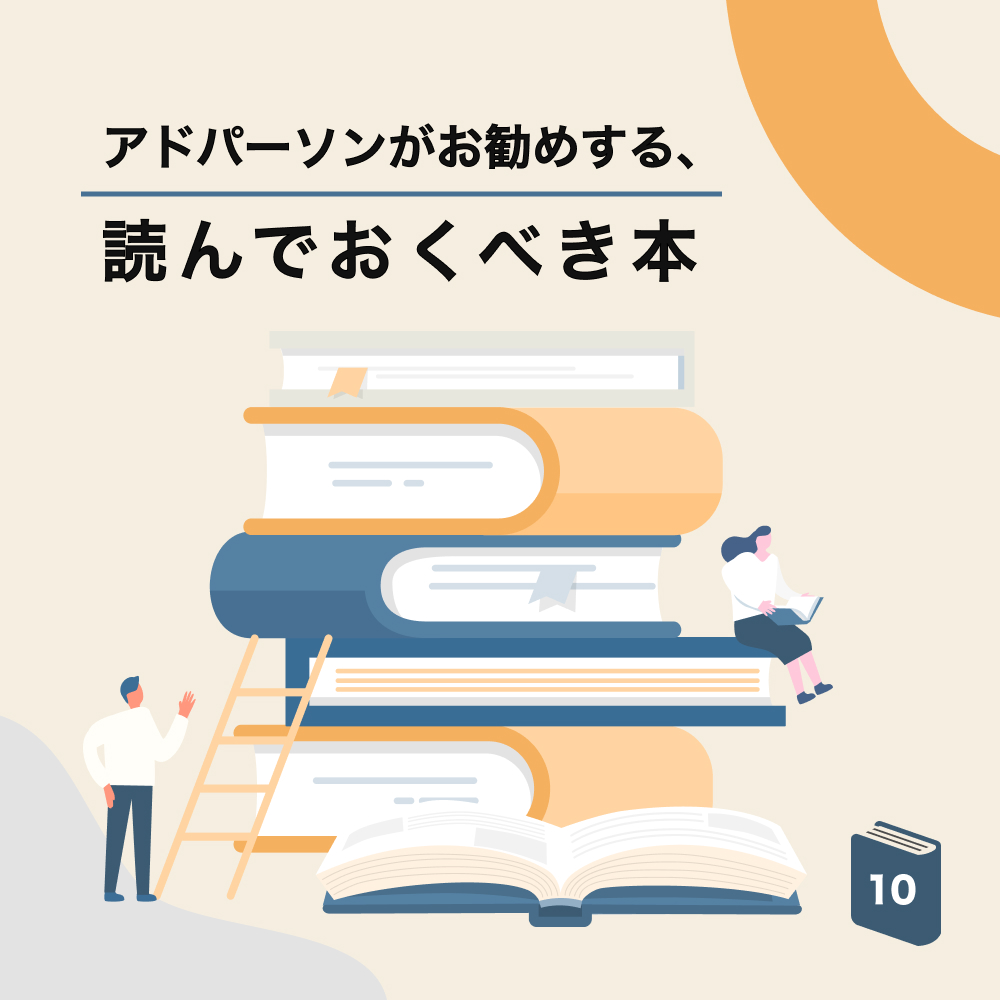仕事中はもちろんのこと、プライベートでも、サブスクの動画サービスの視聴も、リビングのテレビで見るよりは、PCかスマホかタブレット、この年でもゲームもしているので....
仕事中はもちろんのこと、プライベートでも、サブスクの動画サービスの視聴も、リビングのテレビで見るよりは、PCかスマホかタブレット、この年でもゲームもしているので、休みの日にはPCの前でコントローラーを握るかマウスを右手に、と何らかのデバイスに目を向けっぱなしの日々なのですが、本だけはアナログ派から脱することができません。本を手に持ち、目を動かし、ページをめくり、また文字を追う、そんな幼年期から慣れ親しんだ行動様式が何か脳に作用しているのでしょうか。
本を探すときも同じで、ネットで欲しい本にピンポイントでたどり着くのは便利でいいのですが、書店で何気なく本に出逢う、そんな偶然も、かなうのであればいつまでも大事にしたいと思っています。
『共生の作法―会話としての正義―』 井上達夫著(勁草書房)
昨今、毎日のように国内外のニュースで、社会・政治の分断や民主主義への疑問、信頼のゆらぎがあからさまに垣間見えてくる世の中になってしまったように感じられますが、とかく多様な価値観や主張で複雑化してしまった現代社会において、自分の中でも糸が絡まり合ってしまったようで整理がつかず、答えが見つからない人も多いのではないでしょうか。
この本は、いかにして対立する人々が相互に尊重しあい、共に生きることが可能なのか、その原理から解き明かそうとするものです。
とかく相対的なものでしかないと揶揄されがちな「正義」ですが、その本質は本当にそうなのか、「相対主義」とは答えとなり得るかについての論議は、今の世の中にこそ触れておきたいテーマであり、思考を整理するうえで、一定の光を当ててくれるものになるでしょう。
私が最初にこの本を読んだのは大学時代で、その当時は創文社から出版されていましたが、同社の解散により現在では勁草書房より増補新装版が出ています。もし私のつたない文章でも興味を持っていただけたという方は、ぜひそちらを。
『AIの法律』 西村あさひ法律事務所 福岡真之介編著(商事法務)
広告会社にとって、以前として重要なテーマとなっているAIから一冊ですが、AIとそれをめぐる、関連する法律との関係を幅広く扱っている点が魅力の書籍です。
学習や知的財産との関係というメジャーな論点はもちろん、AIが行った契約の攻略や、刑事法との関係、労働法や金融関連法との関係も押さえられており、目次を読むだけでも非常に興味深い内容になっています。
「AIを使おうとしている/使っている」段階で直面するであろう問題が網羅されている点が大きな強みで、既存法制度の整理や実務対応の指針として、また、AIを使った業務上での論点整理をしたいときには、うってつけの書籍と言っていいのではないかと思います。
アメリカではAIとの対話にのめり込んでダメージを被った若年層に関する訴訟が提起されたりもしていますが、AIと倫理についても、テーマとして押さえられています。
『戦闘妖精・雪風』 神林長平著(早川書房)
AIつながりでもう一冊、これはSF小説ですが、日本でもっとも古いSF賞である星雲賞の受賞作です。
正体不明、コミュニケーション不可の異性体と戦う特殊部隊のパイロットが主人公の作品(ただし、主人公が所属するのは戦術電子偵察部隊のため、自機を守る以外の戦闘は行いません)ですが、戦術立案はAIが行い、愛機は戦術判断や空戦時の機動を自律判断において行う中で、主人公たちは、この戦いは果たして人間と異性体との間のものなのだろうかという疑念を深めていきます。更には敵である異性体は人間を認識していないか、付属物としか考えていない可能性まで示唆される始末。
初出が1979年、文庫版の初版が1984年ですが、当時は民生レベルでは(近)未来の技術に過ぎなかったAIや自動運転がここまで身近となり、人間の仕事とのバッティングが生まれている今読んでみると、(変わらない魅力と)かえって実感を与えてくれる名作です。
なお、「グッドラック」「アンブロークン・アロー」「アグレッサーズ」「インサイト」という続編も刊行されていますので、ぜひそちらも手にお取りいただければ。