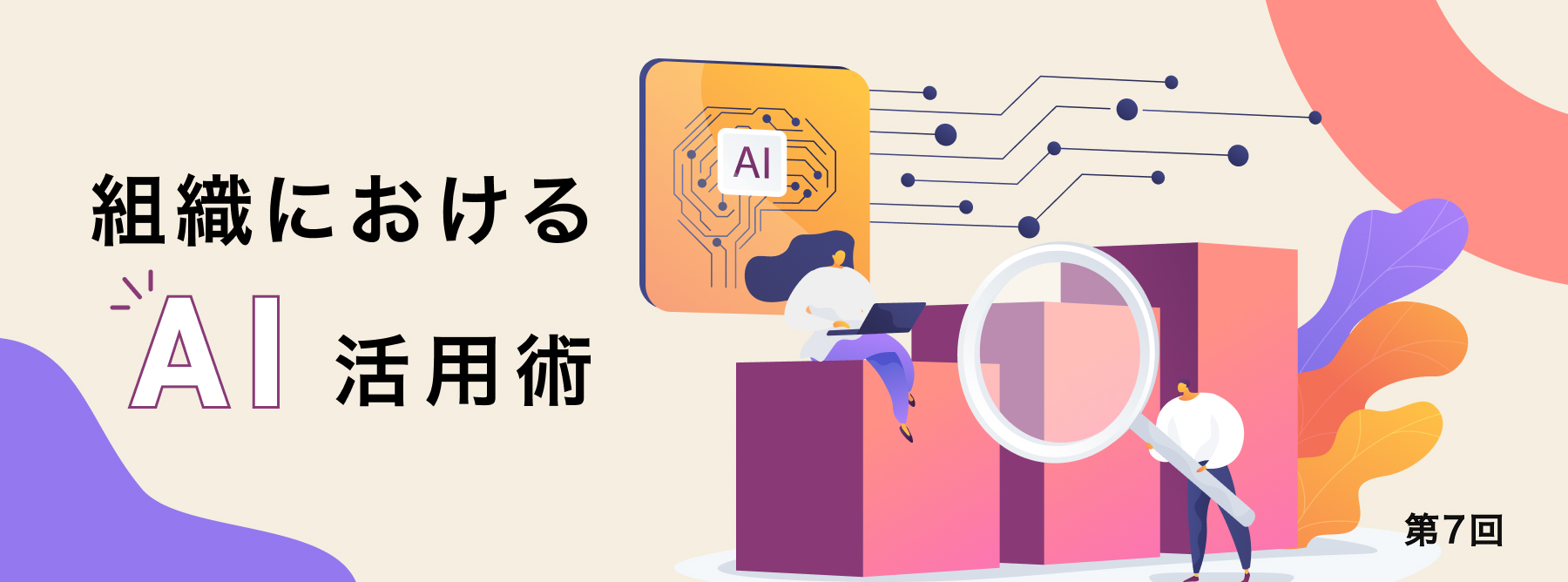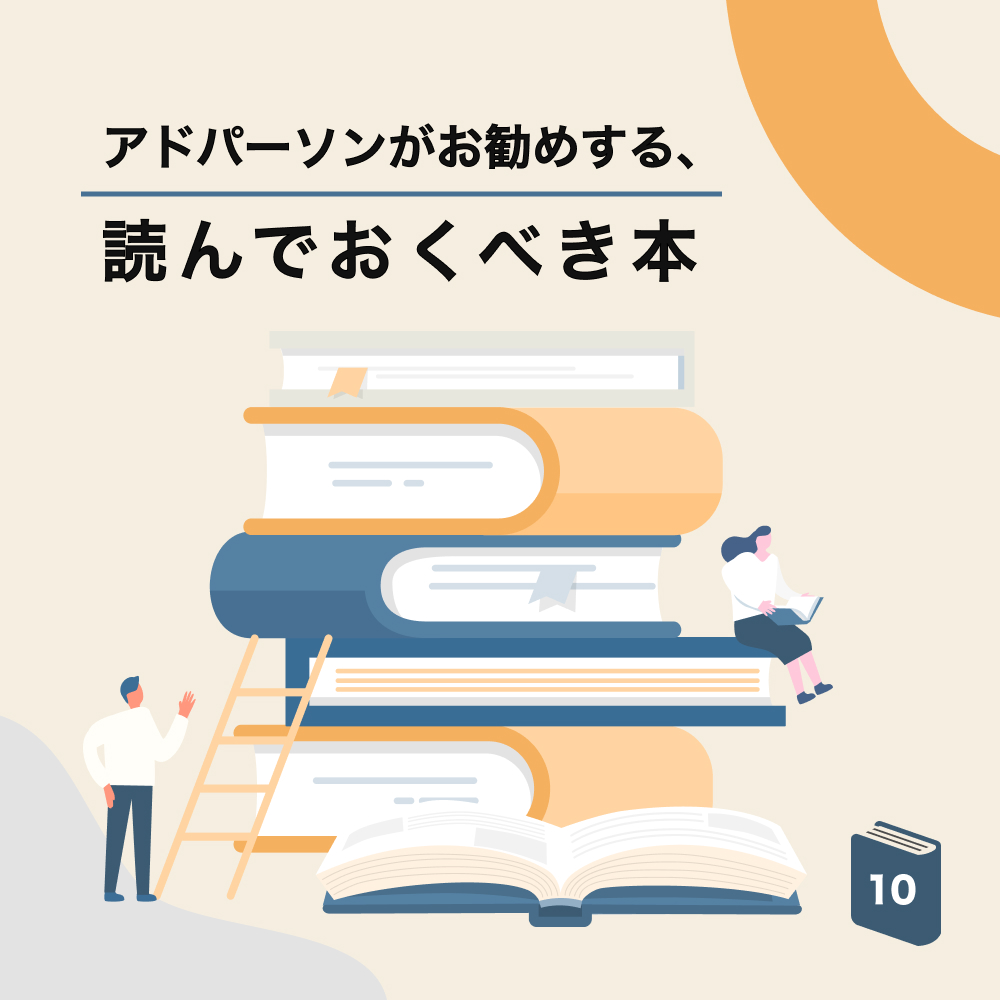DXコンサルティング本部DXコンサルティング局
チーフAIストラテジスト
大手コンサルティングファーム、クリエイティブ系法人向けスタートアップを経て、現職。メディア、Webサービス、通信、エネルギー業界を中心に、DX企画、AI実装、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。 コンサルティング活動の傍ら、社内DX部門にて外部情報発信やAI系スタートアップとの協業に従事。クリエイティブ系法人向けSaaS企業にてCustomer Successを立上げ、契約更新率の大幅改善を達成。新規プロダクトの立ち上げ等も主導。現職においてはDXコンサルティング事業/組織の立ち上げを主導しながら、プロジェクトリード、及び、ブランディング/マーケティング活動に従事。また、博報堂DYグループでAI活用を進めるHCAI Instituteへ所属。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)。
これまでの連載では、いかにして組織内部の従業員のAIリテラシーを高め、日々の業務に活用していくかというテーマを論じてきた。このように個々の従業員の生産性を高め、組織全体のケイパビリティを底上げすることは、間違いなく重要な一手である。
第7回 AIは社外・他部署との接合点で、その真価を発揮する
これまでの連載では、いかにして組織内部の従業員のAIリテラシーを高め、日々の業務に活用していくかというテーマを論じてきた。このように個々の従業員の生産性を高め、組織全体のケイパビリティを底上げすることは、間違いなく重要な一手である。
しかし、AI活用のポテンシャルは、組織内部だけに留まるものではない。
今回は視点を変え、組織の「外」、すなわち社外パートナーや他部署との「接合点」におけるAI活用の可能性について探求したい。
多様な専門家との協働において発生するコミュニケーションコストや認識のズレは、我々が長年頭を悩ませてきた課題であった。この組織間の境界線で発生する非効率を、AIが得意とする「思考の具現化」と「客観的な翻訳」によって解消し、新たな共創の形を生み出すことができる。
そもそも、マーケティングは「接合点」が多い
まず、マーケティングという領域の構造的特性を再認識する必要がある。マーケティング部門は、広告会社、制作会社、コンサルタント、ツールベンダーといった無数の社外パートナー、そして事業部門や営業部門といった社内の他部署と常に連携しながら価値を創出する。要するに、社内外の専門家たちが交わる「接合点」が数多く存在する領域だ。
しかし、異なる背景、専門性、そして暗黙の前提を持つ人々が協働する場では、常にコミュニケーションの齟齬という名の摩擦が生じる。特にコロナ禍以降、テキストベースの非同期的なコミュニケーションが増えたことで、その課題はより一層、顕在化しているといえるだろう。
この接合点で生じるコミュニケーションの非効率を解消し、本来の協働が持つポテンシャルを引き出す上で、AIが重要な役割を果たす。
例えば、「ブリーフィング」における非効率の解消
具体的なシーンを想像してみよう。マーケティング部門から広告会社へ新商品のキャンペーンを依頼する際のオリエンテーションだ。
これまで我々は、自部門で練り上げた戦略や意図を、誤解なく、かつ正確に伝えるためのブリーフィング資料の作成に、時間と労力を費やしてきた。伝えたつもりが伝わっていない、後から質問が噴出して手戻りが発生する、といった経験は誰にでもあるはずだ。
この伝統的なプロセスを、AIは変える力を持つ。
発注側であるマーケティング部門は、AIと共にブリーフを作成できる。AIは、論理的で抜け漏れのない構成を提案するだけでなく、客観的な「第三者」の視点からその内容をレビューしてくれる。「もし私がこのブリーフを初めて受け取る広告会社の人間だとしたら、ここに疑問を持つだろう」といった擬似的なフィードバックを事前に得ることで、資料の解像度を高め、手戻りのリスクを未然に防ぐことが可能になる。
一方で、受注側である広告会社もまた、AIをパートナーとすることができる。受け取ったブリーフをAIと共読解し、論点を整理させ、本質的な質問事項を洗い出す。これにより、Q&Aの質を高め、プロジェクト初期の重要な認識合わせを、より迅速かつ的確に進めることが可能になる。
「提案型」から「共創型」へのシフト
AIがもたらす変化は、前述のブリーフィングのような既存プロセスの効率化に留まらない。よりドラスティックに、協働のあり方そのものを、「提案受領型」から「共創型」へとシフトさせる。
例えば先ほどに引き続き広告会社との協働を考えてみよう。これまでの関係性は、多くの場合、広告会社が複数案を企画・提案し、事業会社がそれを選び、フィードバックするという、ある種の一方通行的な構造であった。しかし、AIが議論の「たたき台」やアイデアの「プロトタイプ」を瞬時に生成できるようになった今、その前提は変わりつつある。
もはや、どちらかが時間をかけて案を練り上げる必要はない。AIが生成したアウトプットを共通のキャンバスとして、両社の担当者がリアルタイムでディスカッションし、共にアイデアを育てていく。そんな「共創」が現実のものとなりつつある。
これは単なる効率化ではない。共に創り上げるプロセスを通じて、双方の納得感とプロジェクトへのコミットメントは深まり、結果としてアウトプットの質そのものを向上させる、本質的な変革といえるだろう。
なぜこれが可能になったのか。それは、AIが異なる組織間の「言語」や「文脈」を客観的に翻訳し、頭の中にある抽象的な思考を、誰もが見て触れる具体的な「形」(テキスト、画像、構成案など)に変換する能力に長けているからに他ならない。この力は、ベンダーとのツール要件定義や、事業部とのサービス企画など、マーケティングにまつわるあらゆる「接合点」に応用できる、普遍的な価値を持っている。

ただし、人間が築く信頼の土台の上で
ここまで、組織の境界線を越えるAI活用の可能性を述べてきた。
だが、最後に極めて重要な点を強調しておきたい。この新たな共創的アプローチを成功させる大前提は、組織と組織、人と人の間に強固な信頼関係が存在することだ。
信頼関係がなければ、他部門や他企業とこのような新たなオペレーション像をともに実現することは決してできない。
人間が築いた信頼という土壌があって初めて、AIと共に新しい協働の形が目指せる。
この領域は、まだ開拓が始まったばかりだ。一社だけでなく、業界全体でこの新たな挑戦に踏み出し、未来のマーケティングプロセスを共に創り上げていくべき時が来ている。