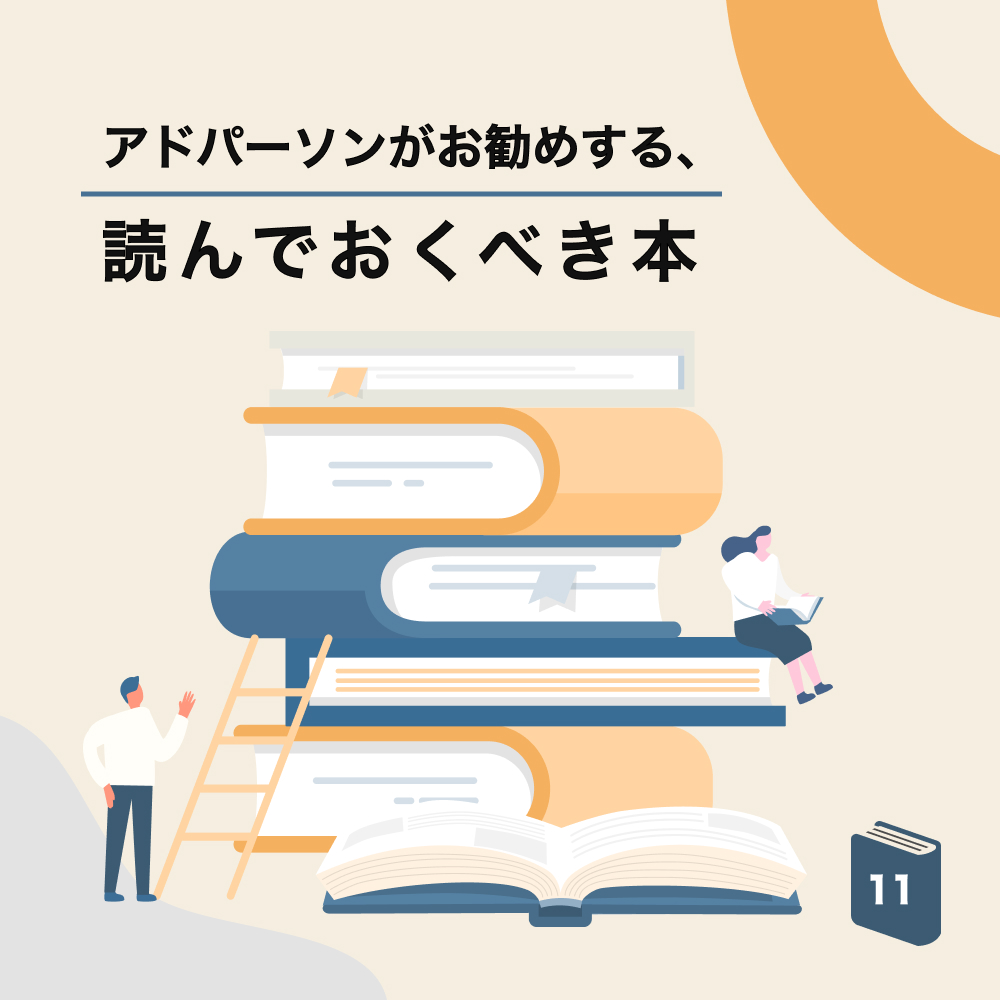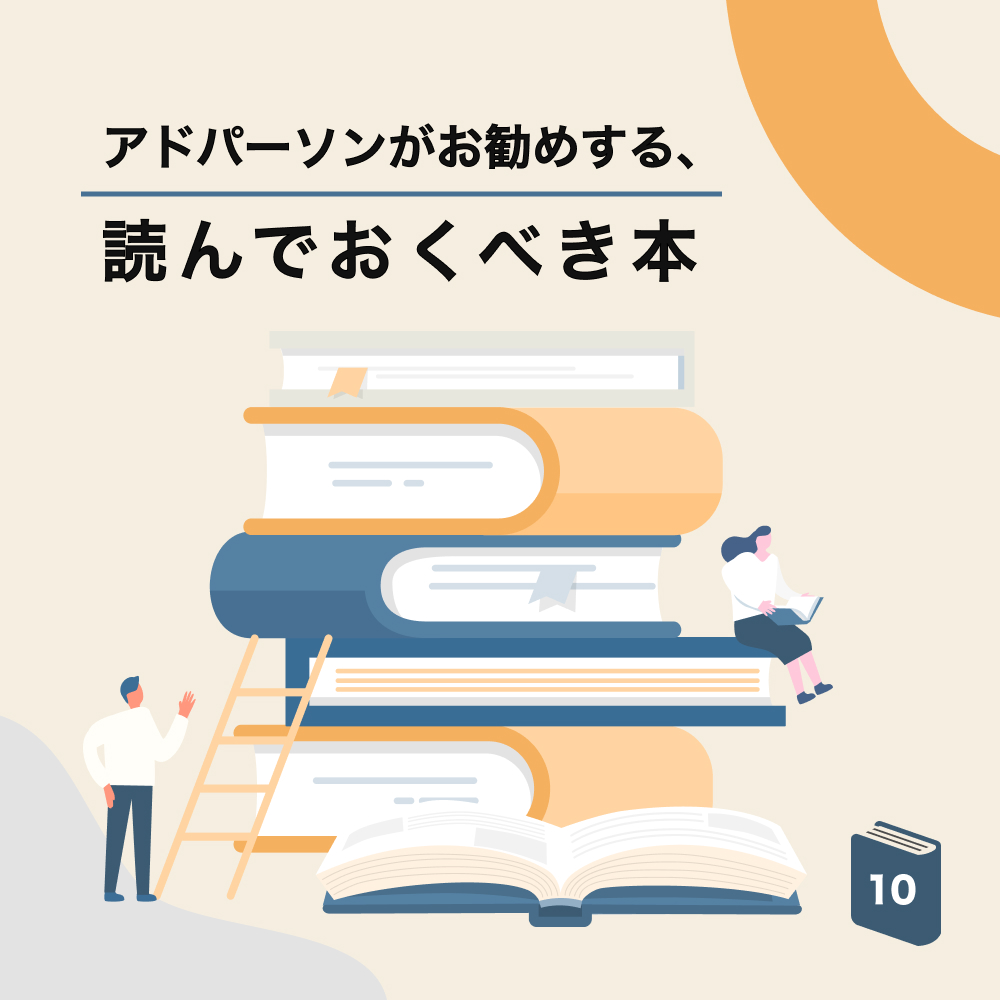DXコンサルティング本部DXコンサルティング局
チーフAIストラテジスト
大手コンサルティングファーム、クリエイティブ系法人向けスタートアップを経て、現職。メディア、Webサービス、通信、エネルギー業界を中心に、DX企画、AI実装、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。 コンサルティング活動の傍ら、社内DX部門にて外部情報発信やAI系スタートアップとの協業に従事。クリエイティブ系法人向けSaaS企業にてCustomer Successを立上げ、契約更新率の大幅改善を達成。新規プロダクトの立ち上げ等も主導。現職においてはDXコンサルティング事業/組織の立ち上げを主導しながら、プロジェクトリード、及び、ブランディング/マーケティング活動に従事。また、博報堂DYグループでAI活用を進めるHCAI Instituteへ所属。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)。
かつてないほどに高まるAIへの熱狂。 私はさまざまな企業の部門や経営層へのコンサルティングをおこなってきた。そのなかで常々感じるのは、マーケティング業界がAI活用の最前線に立ち、企業のDXを牽引する役割を期待されていることだ。
第1回 マーケティング組織は、AI時代の主役だ。
かつてないほどに高まるAIへの熱狂。
私はさまざまな企業の部門や経営層へのコンサルティングをおこなってきた。そのなかで常々感じるのは、マーケティング業界がAI活用の最前線に立ち、企業のDXを牽引する役割を期待されていることだ。実際、企業のマーケティング&セールス部門において、生成AIの導入・投資が先行しているとするガートナーの調査結果(※1)もある(カスタマーサービス部門がもっとも先行しており、次いでマーケティング、セールスとなる)。
だが、最前線であるがゆえに、常に情報不足は深刻だ。誰もが手探りで試行錯誤している。この連載では、そんな現場で奮闘する皆さんに、新たな視点を届けていきたい。
ただし、ここで語るのはAIの技術論ではない。
「AIをどう組織に浸透させるか」というテーマだ。
AI活用は決して開発者だけの話ではなく、人とAIが一緒になって未来の働き方を創っていく「組織論」そのものといえる。
今回の第一回では、なぜマーケティングこそが企業のAI活用の先駆者だと期待されるのかを俯瞰してみよう。
先に結論を述べると、マーケティング領域の特性や課題と、近年のAIの進化が極めて親和性が高いからという理由だ。
まずひとつ目に、マーケティングほど企業の外側、つまり顧客や市場に近い領域は他にない。
生活者のリアルを追いかけ続けるのがマーケターの仕事だが、生活者や顧客と密接に関わり、常に外からインサイトを掴むのは簡単ではない。机上で緻密にペルソナを描いても、実際の生活者像とはズレが生じがちだ。
この積年の難題を突破する力を秘めるのが、生成AIだ。
たとえば、自分たちが描いたペルソナを生成AIにインプットすれば、そのペルソナそっくりのAIと会話できる。いわば「無限壁打ち」や「仮想デプスインタビュー」だ。さらに、人間が読み切れない膨大なインタビューやアンケートのデータをAIが分析して、新たなインサイトを発掘するという使い方も登場している。

次に、マーケティング領域では「専門性や社を跨いだ協働が極めて多い」といえる。
実際、企業で働くマーケターの約90%が、複数の外部パートナー企業と同時並行で連携し、多い場合には15社以上のパートナーと同時にプロジェクトを進めているという調査もあるほどだ(※2)。
広告会社、メディアプランナー、クリエイター、プラットフォーム企業など、異なる専門性を持つ人々が集まると、それぞれの価値観や表現スタイル、専門用語の違いから、スムーズな協働に向けたコミュニケーション課題は、いつでも担当者たちの頭を悩ませてきた。
マーケティング領域は、さまざまな専門家との協働におけるコミュニケーション課題を、いち早く経験する『課題先進領域』だといえる。
だがいま、その課題の解決をAIが助けはじめている。たとえば、会社間の複雑で属人的な発注・受注の与件整理を対話型AIがサポートしたり、机上の抽象的な議論から脱却し、生成AIが具体的な制作物のプロトタイプを作って、より鮮明な共創を促したりすることも可能になった。こうした変化は、会社間の話だけではなく、マーケティング部門と事業部門間の社内連携にも当然ながら役立つであろう。
さらに、マーケティングにおけるAI活用の最大の特長は、「業務効率化の枠を超えられること」にある。たとえば、SalesforceのベニオフCEOは、2024年9月のAll-In SummitでAIを活用したカスタマーサービスエージェントについて述べ、「AIによるサービスエージェントはすでに実用化されている。人間と区別がつかないレベルに達しつつあり、顧客体験を根本から進化させる」と語っている(※3) 博報堂もまた、AIエージェントの普及が購買行動そのものを変革するとして、新しい購買行動モデル『DREAM』を提唱した(※4) 。
このようにAIを直接顧客接点で使えるのも、マーケティング部門ならではの特権なのだ。
ここまで、マーケティング組織が企業全体のAI活用をリードする存在として期待される背景をいくつか紹介した。
大袈裟かもしれないが、私たちは、否が応でもAIとの協働という未踏の地を踏む探検家だ。
いかにマーケティング組織に有利な条件が揃っているといえども、その道のりは決して簡単ではないはずだ。
次回以降の連載では、AI活用を組織的に推進していくための具体的かつユニークな視点やヒントについて、私のコンサルティング経験をもとに、さらに詳しく紹介していく予定だ。たとえば、推進体制の成功事例、優先して取り組むユースケースの考え方、従業員のリスキリングや再配置はどのように考えるか等、ひとつずつ論点を紐解いていきたいと思う。ぜひ楽しみにしていてほしい。
<出典情報>
※1 Gartner、2024年「What Generative AI Means for Business」
※2 WFA、「Agency Rosters Research 2022」
※3 All-In Summit 2024/Dreamforce 2024 基調講演
※4 博報堂 調査レポート「博報堂買物研究所 買物フォーキャスト2025 」(2025年1月21日 )