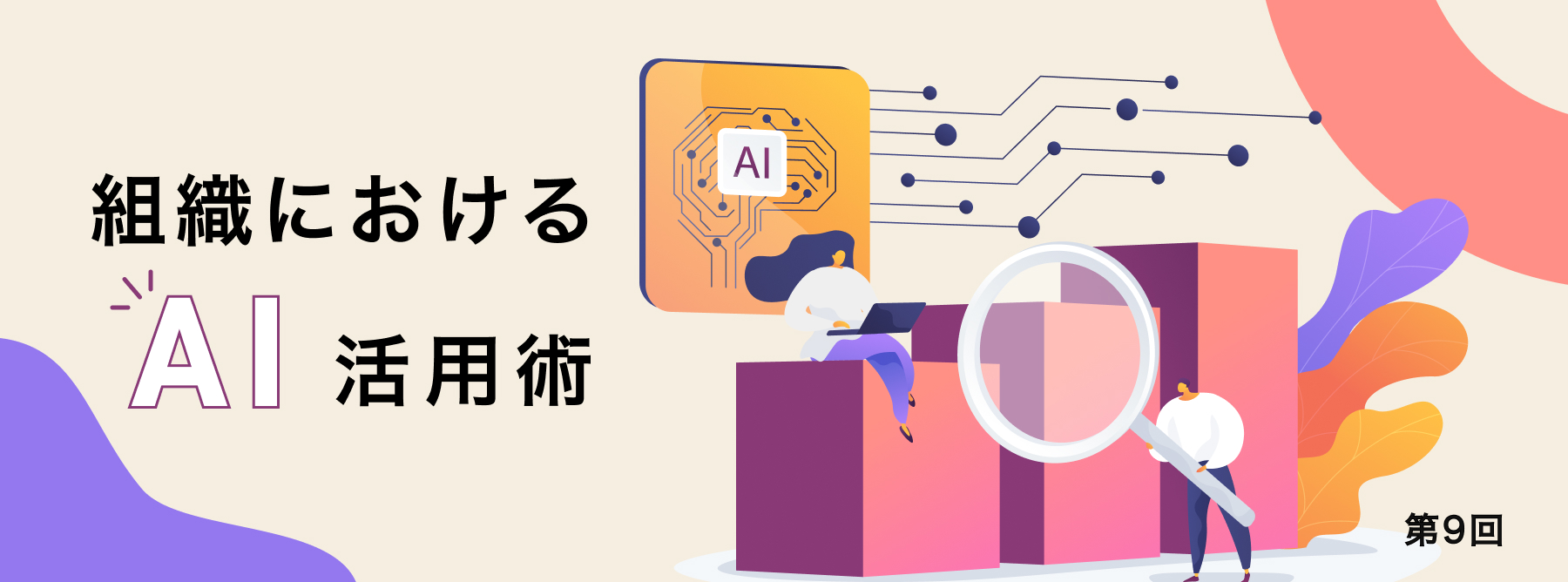DXコンサルティング本部DXコンサルティング局
チーフAIストラテジスト
大手コンサルティングファーム、クリエイティブ系法人向けスタートアップを経て、現職。メディア、Webサービス、通信、エネルギー業界を中心に、DX企画、AI実装、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。 コンサルティング活動の傍ら、社内DX部門にて外部情報発信やAI系スタートアップとの協業に従事。クリエイティブ系法人向けSaaS企業にてCustomer Successを立上げ、契約更新率の大幅改善を達成。新規プロダクトの立ち上げ等も主導。現職においてはDXコンサルティング事業/組織の立ち上げを主導しながら、プロジェクトリード、及び、ブランディング/マーケティング活動に従事。また、博報堂DYグループでAI活用を進めるHCAI Instituteへ所属。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)。
これまでの連載では、いかにしてAIを組織に浸透させ、その力を最大限に引き出すかという、いわば「光」の側面を論じてきた。だが、物事には必ず光と影がある。本稿では、これまでの論調とは一線を画し、AIの「影」の側面に焦点を当てよう。
第9回 組織の思考が均質化する「AIディストピア時代」に抗え
これまでの連載では、いかにしてAIを組織に浸透させ、その力を最大限に引き出すかという、いわば「光」の側面を論じてきた。
だが、物事には必ず光と影がある。
本稿では、これまでの論調とは一線を画し、AIの「影」の側面に焦点を当てよう。
それは、AIとの共創が、意図せずして我々の思考を画一化させ、組織から創造性を奪い、静かなる「ディストピア」へと導く可能性だ。これは技術論ではなく、人間の思考と組織文化の未来に関わる、根源的な問いである。
とあるワークショップでは、8割が同じ”答え”を提出してしまった
このリスクの深刻さを、私は最近とあるワークショップで体験した。「AIと共に考える」をテーマに、20年後の購買体験がどう変化するかを検討するワークショップで、参加者たちは生成AIを壁打ち相手に、未来のアイデアを自由に発想していった。
だが、その結果は僕を愕然とさせた。
提出されたアイデアの実に8割が「個人の嗜好に合わせた、高度なパーソナライゼーション」という、ほぼ同一の結論に収斂していたのだ。
もちろん、パーソナライゼーションが未来の重要な要素であることは間違いない。
しかし、本当にそれだけだろうか。決済手段のさらなる進化、Eコマースとリアル店舗の融合など、未来を構成する要素は無数にあるはずだ。にもかかわらず、なぜこれほどまでに、思考が一つの答えに吸い寄せられてしまったのか。
答えは、彼らが対話したAIの中にあった。
実は、多くの生成AIに「20年後の購買体験の変化は?」と問いかけると、その回答の第一候補として、極めて高い確率で「パーソナライゼーションの進化」が挙げられる。参加者たちは、AIが提示した「最もそれらしい答え」をなぞり、そこから先の多様な可能性を探る機会を逸してしまっていたのかもしれない。
これは、決して彼らの能力が低いからではない。むしろ、AIという強力なツールを前にしたとき、誰もが陥る可能性のある罠なのである。
AIが生成するのは正解—すなわち最もつまらない答えかもしれない
この出来事が示すのは、AIによる「思考の均質化」という、これからの組織が直面するであろう深刻な課題だ。
生成AIは、その仕組み上、学習データの中から最も確率的にありえそうな、いわば「最大公約数的」な回答を生成することを得意とする。それは裏を返せば、最も陳腐で、無難で、つまらない答えともいえるだろう。
その答えは一見すると論理的で、説得力があるように見えるだろう。
しかし、組織の誰もが、そのAIが示す「正解らしきもの」に安易に飛びついてしまったらどうなるか。10人で企画会議を開いても、100人でブレインストーミングをしても、全員が同じスタートラインから、同じ結論に至る。そこにはもはや、多様な視点の衝突から生まれる化学反応も、常識を覆すような独創的な飛躍も存在しない。
新しいアイデアや戦略を生み出すことは、人間の知性が担う最も重要な役割だ。しかし、AIがそのプロセスに介在することで、我々は知らず知らずのうちに、「思考停止」へと誘われているのかもしれない。
思考を失う、ディストピア時代に陥ってはいけない
問題はさらに根深いかもしれない。
AIへの依存は、単にアウトプットを画一化させるだけでなく、我々から「考える力」そのものを奪う可能性があるのだ。
近年のMITの研究では、AIを多用するグループは、AIなしで課題に取り組む際に脳の活動が低下する、つまり「頭が使えなくなっている」可能性が示唆されたという。AIの答えを受け入れるだけの受動的な行為が、自ら問いを立て、仮説を構築し、批判的に思考するという、人間が本来持つ認知能力を錆びつかせてしまうのだ。
興味深いことに同研究では、自らの頭で深く考える習慣を持つ人々は、AIを思考の触媒として能動的に活用する傾向があるという結果も出ている。
だが、組織の大多数を占める人々にとって、それは果たして可能だろうか。むしろ、日々の業務に追われる中で、手軽に「答え」を与えてくれるAIは、思考停止への滑りやすい坂道となり得るのではないか。
このまま、我々が何も手を打たなければ、どのような未来が待っているだろうか。
現場はAIが示す「正解」を横に流すオペレーターになるかもしれない。管理職はAIが提示した最も成功確率の高い戦略オプションを疑うことなく採択するようになるかもしれない。
そのような組織で果たして、予期せぬ変化に対応し、新たな価値を生み出すイノベーションは生まれるだろうか。
AI活用を推進する我々は、この深刻なリスクから決して目を背けてはならない。
特に、生活者のインサイトを深く洞察し、常に新しい価値創造を求められるマーケティング組織にとって、思考の均質化は、その存在意義を揺るがしかねない。
次回以降、この「思考の均質化」というディストピアを避け、AI時代における組織の創造性を守り育てるための、より具体的なアプローチについて論じていきたい。